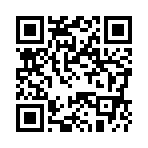2009年06月30日
アカカマスの食べ方
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
私もカマスの淡白な味が好きで、生では塩焼き、または干物にしたものを食することが多いです。料理法としては、薄造りの刺身、塩焼き、天ぷら、フライ、唐揚げ、酒蒸しやホイル焼きなどの蒸し物、煮物などが向いているそうです。
カマスの栄養価は白身魚に並んで優れた蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラルは含まれているそうですが、ビタミンDの含有量が豊富だそうです。
或る料理研究家はカマスの食べ方について、下記のように色々と説明をされていました。
『塩焼きは昔からの料理法ですが、ムニエルにしてソースの味の変化で、こくのある味にも仕上がります。又、唐揚げにしてサラダ味風、マリネー、グラタンに・・。魚の長さを生かして巻物が出来るのも嬉しいですね。脂肪の少ない時期はすり身にして色々な料理を作ることもできます。干物は一塩の一夜干しが最高です。
山陰地方の昔からの料理だそうですが、懐石料理にも出てくる'摘み御寮'というお握りがあります。炊きたてのご飯に揉みワカメを混ぜ、焼いて解した干物を混ぜてつくります。夏の旬の材料を生かした日持ちがよく、食欲をそそり、栄養バランス抜群のファーストフードと自負しております。因みにこの名の由来は御寮さんでも摘みたくなるような美味しさがある所からついたそうです。
冬のカマスは焼き物の代表格は柚庵焼きです。みりん、酒、しょうゆに柚の皮、汁を加えたゆう庵地に漬け込んで焼いた料理です。焼き物、干物も脂がのっていて美味しいです。
ベランダで一夜干しを作って見ませんか。カマスの鱗を落とし、腹側から開きます。頭~尾まで中骨に沿って背の皮ぎりぎりまで包丁を入れて切り開き、内臓を取り出して水洗いをします。次にやや大目に塩を両面に振って、約20分おき、さっと水で塩を洗い流してクリップのついている洗濯干しに下げ、夜~朝明けまでで出来上がりです。表面を指で触って、乾いていれば出来上がりです。うまいが一番という味です。』
ところでカマスの「塩焼き」のコツとしては、次のようにしたらいいそうです。、
『重さの3~4%の振塩にして30分間程度冷蔵庫に入れるか、または、3%ぐらいの食塩水に30分ぐらい浸漬しておくこと。こうすると、塩に触れている間にたんぱく質が凝固して身がしまり、この熟成中にたんぱく質からグルタミン酸やアスパラギン酸が遊離して旨味成分が増える。』
カマス筒焼き
カマス炙り焼き
格安!ブランド通販

アフィリエイトドシロウトの私に手取足とり教えてくれました。

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
私もカマスの淡白な味が好きで、生では塩焼き、または干物にしたものを食することが多いです。料理法としては、薄造りの刺身、塩焼き、天ぷら、フライ、唐揚げ、酒蒸しやホイル焼きなどの蒸し物、煮物などが向いているそうです。
カマスの栄養価は白身魚に並んで優れた蛋白質、脂肪、ビタミン、ミネラルは含まれているそうですが、ビタミンDの含有量が豊富だそうです。
或る料理研究家はカマスの食べ方について、下記のように色々と説明をされていました。
『塩焼きは昔からの料理法ですが、ムニエルにしてソースの味の変化で、こくのある味にも仕上がります。又、唐揚げにしてサラダ味風、マリネー、グラタンに・・。魚の長さを生かして巻物が出来るのも嬉しいですね。脂肪の少ない時期はすり身にして色々な料理を作ることもできます。干物は一塩の一夜干しが最高です。
山陰地方の昔からの料理だそうですが、懐石料理にも出てくる'摘み御寮'というお握りがあります。炊きたてのご飯に揉みワカメを混ぜ、焼いて解した干物を混ぜてつくります。夏の旬の材料を生かした日持ちがよく、食欲をそそり、栄養バランス抜群のファーストフードと自負しております。因みにこの名の由来は御寮さんでも摘みたくなるような美味しさがある所からついたそうです。
冬のカマスは焼き物の代表格は柚庵焼きです。みりん、酒、しょうゆに柚の皮、汁を加えたゆう庵地に漬け込んで焼いた料理です。焼き物、干物も脂がのっていて美味しいです。
ベランダで一夜干しを作って見ませんか。カマスの鱗を落とし、腹側から開きます。頭~尾まで中骨に沿って背の皮ぎりぎりまで包丁を入れて切り開き、内臓を取り出して水洗いをします。次にやや大目に塩を両面に振って、約20分おき、さっと水で塩を洗い流してクリップのついている洗濯干しに下げ、夜~朝明けまでで出来上がりです。表面を指で触って、乾いていれば出来上がりです。うまいが一番という味です。』
ところでカマスの「塩焼き」のコツとしては、次のようにしたらいいそうです。、
『重さの3~4%の振塩にして30分間程度冷蔵庫に入れるか、または、3%ぐらいの食塩水に30分ぐらい浸漬しておくこと。こうすると、塩に触れている間にたんぱく質が凝固して身がしまり、この熟成中にたんぱく質からグルタミン酸やアスパラギン酸が遊離して旨味成分が増える。』
カマス筒焼き
カマス炙り焼き
格安!ブランド通販
アフィリエイトドシロウトの私に手取足とり教えてくれました。
2009年06月29日
魚名:アカカマス
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:30cm
学名:Sphyraena pinguis 英名:Red barracuda
地方名:アカカマサ、ナダカマサ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-カマス科
分布:南日本(琉球列島を除く)東シナ海~南シナ海
<特徴>
体は細長い円筒形に近く、下あごが上あごより前方へとびだし、口先は尖っている。頭は小さく、眼は大きい。体は背の部分が黄褐色で腹側は白い。第1背びれは腹びれの少し後方にある。水深20~60mの沿岸に生息する。夏に浮遊性の卵を産み、1年で25cm、2年で30cmに成長する。イワシ類、エビ・カニ類などを食べる。うろこのきめが粗いことでヤマトカマスと識別できる。旬は秋である。
(「デジタルお魚図鑑」より)
尚、「叺(かます)」とは長方形の筵(むしろ)を二つ折りにして袋状にしたもので、昭和30年代くらいまでは方々で使われているのを見かけたものです。水産の世界でも盛んに使われていたようです。この叺(かます)のように口が大きいことからカマスと命名されたそうです。また体色がヤマトカマス(本カマス)と比べて赤味を帯びていることからアカカマスと言われている所以です。
★叺(かます)の写真はこちら!
『東京のさかな』では下記のような説明がありました。
『アカカマスは関東近辺では相模湾、駿河湾などでもとれ、とてもなじみ深い魚である。当然、市場にあっても見ぬ日はないくらいだ。
その昔は主に塩焼き用、もしくは加工され干物として流通してきた。だから比較的庶民的な魚といえただろう。それが近年徐々に値を上げてきている。これは「カマス=塩焼き用」というのがくずれてきて、刺身や寿司ネタにも利用され始めたからだ。
ちょっと気のきいた料理屋などでは三枚に卸して血合い骨を抜き、皮目をさっとあぶって出す。もしくは軽く締めるなどして出してくる。また干物となってもアカカマスはかなり上等の部類である。また大型の干物材料の確保はなかなか難しいという。』
<アカマスの動画>
1.アカカマスの大群
2.須江、内浦のアカカマス


アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:30cm
学名:Sphyraena pinguis 英名:Red barracuda
地方名:アカカマサ、ナダカマサ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-カマス科
分布:南日本(琉球列島を除く)東シナ海~南シナ海
<特徴>
体は細長い円筒形に近く、下あごが上あごより前方へとびだし、口先は尖っている。頭は小さく、眼は大きい。体は背の部分が黄褐色で腹側は白い。第1背びれは腹びれの少し後方にある。水深20~60mの沿岸に生息する。夏に浮遊性の卵を産み、1年で25cm、2年で30cmに成長する。イワシ類、エビ・カニ類などを食べる。うろこのきめが粗いことでヤマトカマスと識別できる。旬は秋である。
(「デジタルお魚図鑑」より)
尚、「叺(かます)」とは長方形の筵(むしろ)を二つ折りにして袋状にしたもので、昭和30年代くらいまでは方々で使われているのを見かけたものです。水産の世界でも盛んに使われていたようです。この叺(かます)のように口が大きいことからカマスと命名されたそうです。また体色がヤマトカマス(本カマス)と比べて赤味を帯びていることからアカカマスと言われている所以です。
★叺(かます)の写真はこちら!
『東京のさかな』では下記のような説明がありました。
『アカカマスは関東近辺では相模湾、駿河湾などでもとれ、とてもなじみ深い魚である。当然、市場にあっても見ぬ日はないくらいだ。
その昔は主に塩焼き用、もしくは加工され干物として流通してきた。だから比較的庶民的な魚といえただろう。それが近年徐々に値を上げてきている。これは「カマス=塩焼き用」というのがくずれてきて、刺身や寿司ネタにも利用され始めたからだ。
ちょっと気のきいた料理屋などでは三枚に卸して血合い骨を抜き、皮目をさっとあぶって出す。もしくは軽く締めるなどして出してくる。また干物となってもアカカマスはかなり上等の部類である。また大型の干物材料の確保はなかなか難しいという。』
<アカマスの動画>
1.アカカマスの大群
2.須江、内浦のアカカマス
2009年06月28日
アカエイの食べ方
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
アカエイは縄文時代の貝塚からも出土し、昔から食用として利用されてきた魚だそうです。『料理物語』という古書には、「エイ・汁・なます・でんがく・鍋やき・吸い物」とあり、『和漢三才図会』では、「これを煮て食べれば下痢が止まると言ふ。胆は小児の雀目(とりめ)を直す、しばしば試してみたが効き目がある」と薬効を紹介しているそうです。
ヒレの干物の煮込みは、伊勢地方では祭りや祝の膳の一品だったとのことです。また、秋田では干物の煮付けがよく食べられたが、最近では高級料理の一品扱いになってしまったそうです。
<アカエイの料理法>
1.アカエイ料理
2.アカエイの捌き方・料理
3.アカエイの泥焼き
4.アカエイの煮つけ
5.アカエイの甘酢あんかけ
<アカエイの話題>
1.松川浦の特大アカエイ
2.クロコダイルハンター、エイの一撃に倒れる
3.アーウィンのファンが復讐か? エイの尾切られる
エイベックス所属35アーティスト60曲のヒットナンバーがこのCD BOXに集結!「a-box NEO」



アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
アカエイは縄文時代の貝塚からも出土し、昔から食用として利用されてきた魚だそうです。『料理物語』という古書には、「エイ・汁・なます・でんがく・鍋やき・吸い物」とあり、『和漢三才図会』では、「これを煮て食べれば下痢が止まると言ふ。胆は小児の雀目(とりめ)を直す、しばしば試してみたが効き目がある」と薬効を紹介しているそうです。
ヒレの干物の煮込みは、伊勢地方では祭りや祝の膳の一品だったとのことです。また、秋田では干物の煮付けがよく食べられたが、最近では高級料理の一品扱いになってしまったそうです。
<アカエイの料理法>
1.アカエイ料理
2.アカエイの捌き方・料理
3.アカエイの泥焼き
4.アカエイの煮つけ
5.アカエイの甘酢あんかけ
<アカエイの話題>
1.松川浦の特大アカエイ
2.クロコダイルハンター、エイの一撃に倒れる
3.アーウィンのファンが復讐か? エイの尾切られる
エイベックス所属35アーティスト60曲のヒットナンバーがこのCD BOXに集結!「a-box NEO」
2009年06月27日
魚名:アカエイ
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:50cm
学名:Dasyatis akajei 英名:Japanese sting ray
地方名:アヅキエエ、エイガ
脊椎動物門-軟骨魚綱-エイ目-アカエイ科
分布:南日本沿岸、朝鮮半島、台湾、中国沿岸
<生態>
北海道南部から東南アジアまで、東アジア沿岸域に広く分布する。学名の種名"akajei"は和名に由来している。また、フィジーやツバルでも記録がある。
浅い海の砂泥底に生息し、分布域では目にする機会が多い。河口などの汽水域に侵入することもある。普段は砂底に浅く潜り、目と噴水孔、尾だけを砂の上に出す。
泳ぐ時は左右の胸鰭を波打たせ、海底近くを羽ばたくように泳ぐ。食性は肉食性で、貝類、頭足類、多毛類、甲殻類、魚類など底生生物を幅広く捕食する。アサリ等の漁場では食害が問題となることもある。
繁殖形態は多くの軟骨魚類に見られる卵胎生で、メスは交尾後に体内で卵を孵化させる。春から夏にかけて、浅海で5-10匹の稚魚を産む。出産直後の稚魚は体長10cmほどで、背面も腹面も一様に淡褐色だが、既に親と同じ体型をしている。
<形態>
尾を含めた全長は最大で2 mに達する。多くのエイに共通するように、体は上から押しつぶされたように平たく、座布団のような形をしている。左右の胸鰭は緩やかな曲線を描くが、吻は尖っている。
背面は赤褐色-灰褐色で、腹面は白いが、鰭や尾など辺縁部が黄色-橙色になる点で近縁種と区別できる。背面に目があり、噴水孔が目の後方に近接して開く。腹面には鼻孔、口、5対の鰓裂、総排出腔がある。
体表はほとんど滑らかだが背中の正中線付近には小さな棘が並び尾に続く。尾は細長くしなやかな鞭状で、背面に短い棘が列を成して並ぶ。さらに中ほどには数-10cmほどの長い棘が1-2本近接して並ぶ。この長い棘には毒腺があり、刺されると激痛に襲われる。
数週間も痛みが続いたり、アレルギー体質の人はアナフィラキシーショックにより死亡することもある。棘には鋸歯状の「返し」もあり、一度刺さると抜き難い。刺されたらまず毒を絞り、患部を水または湯で洗い流し早急に病院で治療を受ける必要がある。
生体を扱う際は尾を鞭のように払って刺そうとするので充分注意しなければならない。死んだものでも尾には注意が必要である。
(「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」より)
尚、上記で言われているエイ類の毒ですが、ヌクレオチダーゼやホスホジェステラーゼが主成分で、室温に放置すると4分から18分で無毒化するそうです。また、凍結でも無毒化するとのことです。
<動画>
人と戯れる優雅なアカエイ
アカエイ
ワキガ・多汗症治療に上野クリニック

格安!ブランド通販

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:50cm
学名:Dasyatis akajei 英名:Japanese sting ray
地方名:アヅキエエ、エイガ
脊椎動物門-軟骨魚綱-エイ目-アカエイ科
分布:南日本沿岸、朝鮮半島、台湾、中国沿岸
<生態>
北海道南部から東南アジアまで、東アジア沿岸域に広く分布する。学名の種名"akajei"は和名に由来している。また、フィジーやツバルでも記録がある。
浅い海の砂泥底に生息し、分布域では目にする機会が多い。河口などの汽水域に侵入することもある。普段は砂底に浅く潜り、目と噴水孔、尾だけを砂の上に出す。
泳ぐ時は左右の胸鰭を波打たせ、海底近くを羽ばたくように泳ぐ。食性は肉食性で、貝類、頭足類、多毛類、甲殻類、魚類など底生生物を幅広く捕食する。アサリ等の漁場では食害が問題となることもある。
繁殖形態は多くの軟骨魚類に見られる卵胎生で、メスは交尾後に体内で卵を孵化させる。春から夏にかけて、浅海で5-10匹の稚魚を産む。出産直後の稚魚は体長10cmほどで、背面も腹面も一様に淡褐色だが、既に親と同じ体型をしている。
<形態>
尾を含めた全長は最大で2 mに達する。多くのエイに共通するように、体は上から押しつぶされたように平たく、座布団のような形をしている。左右の胸鰭は緩やかな曲線を描くが、吻は尖っている。
背面は赤褐色-灰褐色で、腹面は白いが、鰭や尾など辺縁部が黄色-橙色になる点で近縁種と区別できる。背面に目があり、噴水孔が目の後方に近接して開く。腹面には鼻孔、口、5対の鰓裂、総排出腔がある。
体表はほとんど滑らかだが背中の正中線付近には小さな棘が並び尾に続く。尾は細長くしなやかな鞭状で、背面に短い棘が列を成して並ぶ。さらに中ほどには数-10cmほどの長い棘が1-2本近接して並ぶ。この長い棘には毒腺があり、刺されると激痛に襲われる。
数週間も痛みが続いたり、アレルギー体質の人はアナフィラキシーショックにより死亡することもある。棘には鋸歯状の「返し」もあり、一度刺さると抜き難い。刺されたらまず毒を絞り、患部を水または湯で洗い流し早急に病院で治療を受ける必要がある。
生体を扱う際は尾を鞭のように払って刺そうとするので充分注意しなければならない。死んだものでも尾には注意が必要である。
(「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」より)
尚、上記で言われているエイ類の毒ですが、ヌクレオチダーゼやホスホジェステラーゼが主成分で、室温に放置すると4分から18分で無毒化するそうです。また、凍結でも無毒化するとのことです。
<動画>
人と戯れる優雅なアカエイ
アカエイ
ワキガ・多汗症治療に上野クリニック
格安!ブランド通販
2009年06月26日
魚名:アカイサキ
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:40cm
学名:Caprodon schlegelii 英名:Schlegel`s red bass
地方名:カライッサキ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ハタ科
分布:南日本、台湾、ハワイ諸島、オーストラリア、チリ 大きさ:40cm
<特徴>
ハタ類にしては体がやや平たく、高い。雄の背びれに黒い班点があるが、数・形・大きさは変化する。ベラの仲間みたいに雌雄で体色が異なる。雌では黒斑はなく、黄赤色である。近海の比較的深い岩礁の間に群れで生息している。舌の上にも歯があり、甲殻類や小魚を食べる。
沖釣りでキンメダイやトゴットメバルにまじって釣れる。夏に底引き網で漁獲できるが1度に多くは獲れない。味は人により好き嫌いがあり、まずいといわれるが成長段階によっては味付けの工夫次第でおいしく食べることができる。 (「デジタルお魚図鑑」より)
<良く利用される調理方法>
刺身、霜造り、ムニエル、ポアレ、煮付けなど。 非常に硬い身質です。刺身にするのも、薄く切った方が美味しく食べれます。また、皮目もおいしいので積極的に皮も使うといいようです。油との相性も非常に良く、洋食素材としても好まれます。
ネット上で下記のような料理法が紹介されていました。
1.アカイサキの刺身
2.アカイサキのオリーブオイル焼き
3.アカイサキの中華風あんかけ
4.アカイサキのレモンソテー:アカイサキのウロコ、内臓を取り除き、汚れを洗い流し、3枚におろします。両面に塩・コショウをして、薄力粉を全体に薄く付け、余分な粉は落としておきます。 フライパンにオリーブオイルを引き、両面を焼きます。
焦げ目が付いたら取り出し、フライパンの油をきれいにふき取り、再びフライパンにオリーブオイルを入れ、ニンニクを加えて熱し香りを移します。 そこに魚を戻し、バター、白ワイン、イタリアンパセリのみじん切り、レモンスライスを加え煮つめます。最後に塩コショウで味を調て出来上がり。
5.アカイサキのしゃぶしゃぶ:皮をつけたままでも、皮を剥いでも、どちらでもお好みで。皮がついている場合は、皮のほうからしゃぶしゃぶして、皮は硬いところもあるので、お好みでしゃぶしゃぶする時間は考えて!もみじおろしにポン酢で食べてください!!
6.アカイサキのムニエル:三枚におろして塩・粒コショウをし、小麦粉を付けて下ごしらえをしておきます。にんにくのスライスを少し油で炒めて、きつね色になったら他に移しておいて、炒めた油も使い、バターを溶かし、皮のほうからこんがりと焼きます。
両面やったら、白ワインでも日本酒でもあるほうを多めにかけ、アルコールが飛んだら、醤油で味付けします。家にオイスターソースがある方は少々いれると尚おいしいです。
BodyQuestのボディデザインプログラム

ファンタジスタ!ブランド高価買取

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:40cm
学名:Caprodon schlegelii 英名:Schlegel`s red bass
地方名:カライッサキ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ハタ科
分布:南日本、台湾、ハワイ諸島、オーストラリア、チリ 大きさ:40cm
<特徴>
ハタ類にしては体がやや平たく、高い。雄の背びれに黒い班点があるが、数・形・大きさは変化する。ベラの仲間みたいに雌雄で体色が異なる。雌では黒斑はなく、黄赤色である。近海の比較的深い岩礁の間に群れで生息している。舌の上にも歯があり、甲殻類や小魚を食べる。
沖釣りでキンメダイやトゴットメバルにまじって釣れる。夏に底引き網で漁獲できるが1度に多くは獲れない。味は人により好き嫌いがあり、まずいといわれるが成長段階によっては味付けの工夫次第でおいしく食べることができる。 (「デジタルお魚図鑑」より)
<良く利用される調理方法>
刺身、霜造り、ムニエル、ポアレ、煮付けなど。 非常に硬い身質です。刺身にするのも、薄く切った方が美味しく食べれます。また、皮目もおいしいので積極的に皮も使うといいようです。油との相性も非常に良く、洋食素材としても好まれます。
ネット上で下記のような料理法が紹介されていました。
1.アカイサキの刺身
2.アカイサキのオリーブオイル焼き
3.アカイサキの中華風あんかけ
4.アカイサキのレモンソテー:アカイサキのウロコ、内臓を取り除き、汚れを洗い流し、3枚におろします。両面に塩・コショウをして、薄力粉を全体に薄く付け、余分な粉は落としておきます。 フライパンにオリーブオイルを引き、両面を焼きます。
焦げ目が付いたら取り出し、フライパンの油をきれいにふき取り、再びフライパンにオリーブオイルを入れ、ニンニクを加えて熱し香りを移します。 そこに魚を戻し、バター、白ワイン、イタリアンパセリのみじん切り、レモンスライスを加え煮つめます。最後に塩コショウで味を調て出来上がり。
5.アカイサキのしゃぶしゃぶ:皮をつけたままでも、皮を剥いでも、どちらでもお好みで。皮がついている場合は、皮のほうからしゃぶしゃぶして、皮は硬いところもあるので、お好みでしゃぶしゃぶする時間は考えて!もみじおろしにポン酢で食べてください!!
6.アカイサキのムニエル:三枚におろして塩・粒コショウをし、小麦粉を付けて下ごしらえをしておきます。にんにくのスライスを少し油で炒めて、きつね色になったら他に移しておいて、炒めた油も使い、バターを溶かし、皮のほうからこんがりと焼きます。
両面やったら、白ワインでも日本酒でもあるほうを多めにかけ、アルコールが飛んだら、醤油で味付けします。家にオイスターソースがある方は少々いれると尚おいしいです。
BodyQuestのボディデザインプログラム
ファンタジスタ!ブランド高価買取
2009年06月25日
アカアマダイの食べ方
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
市場の専門家はアカアマダイは鮮魚では余り旨くないので、購入したならウロコは取らぬまま背中から2つ割り、開いて軽く塩をして、また身を閉じる。これを一晩寝かすと「一汐ぐじ」となるそうです。
それはともかく、ネット上で探して見ましたら色々な料理法がありましたので、下記に一部を紹介いたします。
1.あまだいの酒蒸し
2.甘鯛の干物
3.甘鯛飯(あまだいめし)
4.甘鯛の煮付け」
5.甘鯛のみぞれ蒸し
6.アマダイの塩焼きの
7.甘鯛のバター焼き
8.甘鯛の味噌漬け卵の黄身焼き
9.アマダイと柿のシェリーヴィネガー和え
10.甘鯛のムニエル 黄パプリカのソース
<YouTube動画>
小田原活魚 アマダイ&ウツボ
アマダイ釣り


アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
市場の専門家はアカアマダイは鮮魚では余り旨くないので、購入したならウロコは取らぬまま背中から2つ割り、開いて軽く塩をして、また身を閉じる。これを一晩寝かすと「一汐ぐじ」となるそうです。
それはともかく、ネット上で探して見ましたら色々な料理法がありましたので、下記に一部を紹介いたします。
1.あまだいの酒蒸し
2.甘鯛の干物
3.甘鯛飯(あまだいめし)
4.甘鯛の煮付け」
5.甘鯛のみぞれ蒸し
6.アマダイの塩焼きの
7.甘鯛のバター焼き
8.甘鯛の味噌漬け卵の黄身焼き
9.アマダイと柿のシェリーヴィネガー和え
10.甘鯛のムニエル 黄パプリカのソース
<YouTube動画>
小田原活魚 アマダイ&ウツボ
アマダイ釣り
2009年06月24日
魚名:アカアマダイ
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
大きさ:45cm
学名:Branchiostegus japonicus 英名:Blanquillo
地方名:アカクヅナ、アカゴツナ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アマダイ科
分布:南日本~南・東シナ海
私は、この魚をあまり食べたことがありませんが、一般に「アマダイ」と言えば基本的にアカアマダイを指すようです。国内で主に食用となるアマダイには「シロアマダイ(白)」「アカアマダイ(赤)」「キアマダイ(黄)」の3種だそうです。
昔はシロアマダイが最高値、最上位とされていたそうですが、最近ではアカアマダイと変わらないそうです。ともに非常に高価となっています。またキアマダイは珍しいようで、一定の評価はされていませんが、こちらも高級魚だそうです。
関東地方ではあまり利用されていないようですが、関西では古くから高級魚として料亭などでよく提供されています。特に京料理などには欠くことの出来ないもので、若狭(福井県)で獲れる物を「若狭ぐじ」と言って珍重しています。
<特徴>
『アカアマダイは東シナ海を中心に、日本海では青森県まで生息している温帯性の魚です。名前のとおり、体全体が赤色を帯びていて、眼の後にある三角形の銀白色の斑紋、尾びれの4、5本の黄色い縦縞が特徴です。
アマダイと言う名前の由来は身に上品な甘みがあることや魚の横顔を見ると頭を眼のすぐ前で切り落とした様な顔つきをしており、頬被りした尼僧に似ていることからとされています。
島根県ではアカアマダイのことを「コビル」と呼んでいます。「コビル」とはアカアマダイが鯛と名前のつくほかの魚に比べて大きくならないことからついた呼び名のようです。
このほかでは「クズナ」とも呼ばれています。古書には「屈頭魚(くずな)」と書かれており、頭がへこんだように見えることからこう呼ばれるようになったのではないでしょうか。』
(島根のさかな (島根の魚)より)
しかし、アカアマダイも近海ものだけでなく中国からの輸入も多いようです。「東京のさかな」では下記のような説明がされています。
『関東の市場では見かけない日はないほどに頻繁に入荷してくる。非常に値の高い魚なので、どうも産地よりも中央での消費が多いように思える。
本来アマダイは西日本で珍重されてきた魚である。例えば東京湾、相模湾などでもとれるのだが、ほんの四半世紀前までは浜での値は安く、また取り扱い自体に不慣れであったように思われる。それが徐々にアマダイの地位が上がってきたのは、関東の料理店が関西の勢力に席巻されてきたからだろう。
これを「一汐にする」「昆布締め」「若狭焼き」「蒸しもの」にするなど関西割烹、京料理にはなくてはならないものだ。今では「ハモの骨切り」が関東でも普通に行われると同じように、京風に「ぐじ」はありきたりな素材である。
とうぜん使う料理店が増えれば価格が上がるわけで、もっとも近い産地である相模湾のものなど、ときにキロ当たり10000円を超えることもある。この値段のものを扱えるのは唯一築地を始め東京都内なのであり、浜で揚がるや都心行きとなる。
国産ものよりも量的に多いと思われるのが中国などからの輸入もの。冷凍、チルドなどで入荷してくる。当然、昆布締めなどには使えないが、焼き物、蒸しものには充分利用できる。
一般に干物などに使われるのは中国からの輸入品。築地などではチルド、冷凍とも普通に見られる。アカアマダイの場合は冷凍、または輸入ものでもけっして安くはなく、キロ当たり1500円から、冷凍でも1000円前後となる。国内でとれなくなったものを輸入していることになる。』


アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
大きさ:45cm
学名:Branchiostegus japonicus 英名:Blanquillo
地方名:アカクヅナ、アカゴツナ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アマダイ科
分布:南日本~南・東シナ海
私は、この魚をあまり食べたことがありませんが、一般に「アマダイ」と言えば基本的にアカアマダイを指すようです。国内で主に食用となるアマダイには「シロアマダイ(白)」「アカアマダイ(赤)」「キアマダイ(黄)」の3種だそうです。
昔はシロアマダイが最高値、最上位とされていたそうですが、最近ではアカアマダイと変わらないそうです。ともに非常に高価となっています。またキアマダイは珍しいようで、一定の評価はされていませんが、こちらも高級魚だそうです。
関東地方ではあまり利用されていないようですが、関西では古くから高級魚として料亭などでよく提供されています。特に京料理などには欠くことの出来ないもので、若狭(福井県)で獲れる物を「若狭ぐじ」と言って珍重しています。
<特徴>
『アカアマダイは東シナ海を中心に、日本海では青森県まで生息している温帯性の魚です。名前のとおり、体全体が赤色を帯びていて、眼の後にある三角形の銀白色の斑紋、尾びれの4、5本の黄色い縦縞が特徴です。
アマダイと言う名前の由来は身に上品な甘みがあることや魚の横顔を見ると頭を眼のすぐ前で切り落とした様な顔つきをしており、頬被りした尼僧に似ていることからとされています。
島根県ではアカアマダイのことを「コビル」と呼んでいます。「コビル」とはアカアマダイが鯛と名前のつくほかの魚に比べて大きくならないことからついた呼び名のようです。
このほかでは「クズナ」とも呼ばれています。古書には「屈頭魚(くずな)」と書かれており、頭がへこんだように見えることからこう呼ばれるようになったのではないでしょうか。』
(島根のさかな (島根の魚)より)
しかし、アカアマダイも近海ものだけでなく中国からの輸入も多いようです。「東京のさかな」では下記のような説明がされています。
『関東の市場では見かけない日はないほどに頻繁に入荷してくる。非常に値の高い魚なので、どうも産地よりも中央での消費が多いように思える。
本来アマダイは西日本で珍重されてきた魚である。例えば東京湾、相模湾などでもとれるのだが、ほんの四半世紀前までは浜での値は安く、また取り扱い自体に不慣れであったように思われる。それが徐々にアマダイの地位が上がってきたのは、関東の料理店が関西の勢力に席巻されてきたからだろう。
これを「一汐にする」「昆布締め」「若狭焼き」「蒸しもの」にするなど関西割烹、京料理にはなくてはならないものだ。今では「ハモの骨切り」が関東でも普通に行われると同じように、京風に「ぐじ」はありきたりな素材である。
とうぜん使う料理店が増えれば価格が上がるわけで、もっとも近い産地である相模湾のものなど、ときにキロ当たり10000円を超えることもある。この値段のものを扱えるのは唯一築地を始め東京都内なのであり、浜で揚がるや都心行きとなる。
国産ものよりも量的に多いと思われるのが中国などからの輸入もの。冷凍、チルドなどで入荷してくる。当然、昆布締めなどには使えないが、焼き物、蒸しものには充分利用できる。
一般に干物などに使われるのは中国からの輸入品。築地などではチルド、冷凍とも普通に見られる。アカアマダイの場合は冷凍、または輸入ものでもけっして安くはなく、キロ当たり1500円から、冷凍でも1000円前後となる。国内でとれなくなったものを輸入していることになる。』
2009年06月23日
魚名:アカアジ
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
大きさ:30cm
学名:Decapterus akaadsi 英名:潤タ潤タ
地方名:
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アジ科
分布:南・東シナ海、九州近海
<特徴>
『ちょっと見ただけだと尾ビレが赤いマアジみたいですが、尾ビレの付け根に小さなヒレがあり、実際はムロアジのほうがマアジより近い仲間です。
相模湾のビシアジ釣りで時々マアジに混じってきます。写真の魚もマアジ狙いに食い付いてきたものです。
マアジとの違いは尾ビレが赤いのと尾ビレの付け根に小さなヒレがある以外に、体色がやや赤っぽいです。あと眼が光ったり、光の具合によっては瞳に透明感がでるときがあります。
これは眼の奥に光を反射増幅させるためのタペタムと呼ばれる器官があるためで、暗い所で視力を確保するためのものです。ネコの眼が光るのもこれと同じです。
コイツは水深のやや深い所に生息しているため、そのための適応かもしれません。深海に住むバラムツやキンメダイなどわりと多くの魚にもこのタペタム器官が存在します。』
(独善的魚類図鑑より)
<良く利用される調理方法>
刺身、たたき、なめろう、焼き物、唐揚げ、煮付けなど。 加熱するとふわっとした身質で、少しパサつくような感じがしますが、それがおいしいと感じる人も多いようです。
アジのレシピ集
ナイトライフをサポートします!【Love Again】

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
大きさ:30cm
学名:Decapterus akaadsi 英名:潤タ潤タ
地方名:
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アジ科
分布:南・東シナ海、九州近海
<特徴>
『ちょっと見ただけだと尾ビレが赤いマアジみたいですが、尾ビレの付け根に小さなヒレがあり、実際はムロアジのほうがマアジより近い仲間です。
相模湾のビシアジ釣りで時々マアジに混じってきます。写真の魚もマアジ狙いに食い付いてきたものです。
マアジとの違いは尾ビレが赤いのと尾ビレの付け根に小さなヒレがある以外に、体色がやや赤っぽいです。あと眼が光ったり、光の具合によっては瞳に透明感がでるときがあります。
これは眼の奥に光を反射増幅させるためのタペタムと呼ばれる器官があるためで、暗い所で視力を確保するためのものです。ネコの眼が光るのもこれと同じです。
コイツは水深のやや深い所に生息しているため、そのための適応かもしれません。深海に住むバラムツやキンメダイなどわりと多くの魚にもこのタペタム器官が存在します。』
(独善的魚類図鑑より)
<良く利用される調理方法>
刺身、たたき、なめろう、焼き物、唐揚げ、煮付けなど。 加熱するとふわっとした身質で、少しパサつくような感じがしますが、それがおいしいと感じる人も多いようです。
アジのレシピ集
ナイトライフをサポートします!【Love Again】
2009年06月22日
アオリイカに関する動画
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
釣って面白い、食べて美味しい「アオリイカ」は大人気ですから、数々の動画があります。その中のごく一部を紹介します。
1.アオリイカ料理編
アオリイカを使った料理に挑戦
2.アオリイカ実践編
釣り方なんて簡単だ!
3.アオリイカ準備編
道具・仕掛けをcheckしよう
(「特集アオリイカ 今月の狙い釣り:@
niftyつり」より)
YouTube動画
アオリイカエギングノウハウ紹介12アワセの方法
Duel Movie の 笛木展雄 エギング
秋冬の日中エギング講座 講師:杉江徳麿
アオリイカ産卵


30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
釣って面白い、食べて美味しい「アオリイカ」は大人気ですから、数々の動画があります。その中のごく一部を紹介します。
1.アオリイカ料理編
アオリイカを使った料理に挑戦
2.アオリイカ実践編
釣り方なんて簡単だ!
3.アオリイカ準備編
道具・仕掛けをcheckしよう
(「特集アオリイカ 今月の狙い釣り:@
niftyつり」より)
YouTube動画
アオリイカエギングノウハウ紹介12アワセの方法
Duel Movie の 笛木展雄 エギング
秋冬の日中エギング講座 講師:杉江徳麿
アオリイカ産卵
2009年06月21日
アオリイカ「磯打ち網漁」
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
アオリイカのオモシロイ漁法として、「磯打ち網漁」始まると題して、下記のような記事が紹介されていました。(5月11日17時16分配信 紀伊民報より)
『和歌山県串本町津荷や田原の海岸で今月から、海面を棒でたたいて、アオリイカを網に追い込む「磯打ち網漁」が始まった。7月下旬まで続く。
海草類が生えた磯に産卵のため近づくアオリイカを狙った漁法で、この季節の風物詩となっている。長さ約50センチの木の棒「追太棒」で海面をたたき、張り巡らせた網に追い込む。
和歌山東漁協津荷支所では、8戸がくじ引きで決めた4カ所の漁場で、毎日交代で漁をしている。水揚げ量は天候や潮加減に左右される。よく捕れる場所では、1日に何回も漁に出ることもあるという。
漁歴45年の尾中一朗さん(76)と妻の明美さん(69)は8日、今シーズン2回目の漁に出た。漁港周辺に約150メートルの網を張り巡らせ、テンポよく追太棒を海面に打ち付けると水しぶきが上がった。この日は約30匹が捕れた。
尾中さんによると、8戸のうちほとんどが夫婦で漁をしているという。「夫婦の息が大事。大きいのが捕れた時はやっぱりうれしい」と話している。
アオリイカの大きさは平均2・5キロで例年並み。浜値も1キロ当たり約1500円で、例年並み。以前は、2000円以上することもあったが、最近は安値傾向という。』
追太棒で海面をたたく漁師(和歌山県串本町津荷で)の写真
また、「千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の漁獲特性」と題して、下記のような説明がありました。(秋山 清二, 貝原 智志, 有元 貴文; “千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の漁獲特性”, 日本水産学会誌, Vol. 70, pp.865-871 (2004) )
『要旨: 千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の操業方法と漁獲物を調査した。操業には内網目合85mm, 外網目合360mmの三枚網が使用された。漁場は水深4~12mのアマモ場であった。
操業過程は投網, 駆集, 揚網の3過程に分けられた。2002年と2003年の363回の操業で, アオリイカ1491個体, その他996個体が漁獲された。個体数比の投棄率は17%であった。
アオリイカの平均外套背長は28.0±5.8cmであった。外套背長16cm以下の個体は漁獲されなかった。アオリイカの95%は袋状になった内網で漁獲された。』
アオリイカ料理


30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
アオリイカのオモシロイ漁法として、「磯打ち網漁」始まると題して、下記のような記事が紹介されていました。(5月11日17時16分配信 紀伊民報より)
『和歌山県串本町津荷や田原の海岸で今月から、海面を棒でたたいて、アオリイカを網に追い込む「磯打ち網漁」が始まった。7月下旬まで続く。
海草類が生えた磯に産卵のため近づくアオリイカを狙った漁法で、この季節の風物詩となっている。長さ約50センチの木の棒「追太棒」で海面をたたき、張り巡らせた網に追い込む。
和歌山東漁協津荷支所では、8戸がくじ引きで決めた4カ所の漁場で、毎日交代で漁をしている。水揚げ量は天候や潮加減に左右される。よく捕れる場所では、1日に何回も漁に出ることもあるという。
漁歴45年の尾中一朗さん(76)と妻の明美さん(69)は8日、今シーズン2回目の漁に出た。漁港周辺に約150メートルの網を張り巡らせ、テンポよく追太棒を海面に打ち付けると水しぶきが上がった。この日は約30匹が捕れた。
尾中さんによると、8戸のうちほとんどが夫婦で漁をしているという。「夫婦の息が大事。大きいのが捕れた時はやっぱりうれしい」と話している。
アオリイカの大きさは平均2・5キロで例年並み。浜値も1キロ当たり約1500円で、例年並み。以前は、2000円以上することもあったが、最近は安値傾向という。』
追太棒で海面をたたく漁師(和歌山県串本町津荷で)の写真
また、「千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の漁獲特性」と題して、下記のような説明がありました。(秋山 清二, 貝原 智志, 有元 貴文; “千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の漁獲特性”, 日本水産学会誌, Vol. 70, pp.865-871 (2004) )
『要旨: 千葉県館山湾におけるアオリイカ狩刺網の操業方法と漁獲物を調査した。操業には内網目合85mm, 外網目合360mmの三枚網が使用された。漁場は水深4~12mのアマモ場であった。
操業過程は投網, 駆集, 揚網の3過程に分けられた。2002年と2003年の363回の操業で, アオリイカ1491個体, その他996個体が漁獲された。個体数比の投棄率は17%であった。
アオリイカの平均外套背長は28.0±5.8cmであった。外套背長16cm以下の個体は漁獲されなかった。アオリイカの95%は袋状になった内網で漁獲された。』
アオリイカ料理
2009年06月20日
魚名:アオリイカ
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
大きさ:40cm
学名:Sepioteuthis lessoniana 英名:Big fin reef squid
地方名:ミズイカ、モイカ、バショウイカ
軟体動物門-頭足綱-ツツイカ目-ヤリイカ科
分布:北海道南部以南の各地、インド・西太平洋の温・熱帯域
<特徴>
『胴長は約40-45cm。大きいものでは50cm以上、重さは6kg以上に達する。沿岸域に生息するイカとしては大型の部類に入る。
胴が丸みを帯び、胴の縁に渡って半円形のひれを持つ。外見はコウイカに似るが、甲は薄くて透明な軟甲である。雄の背中には白色の短い横線模様が散在するが、雌は横線模様が不明瞭である。
標準和名のアオリイカは漢字では障泥烏賊と書くが、この名前はひれの色や形が障泥(あおり)と呼ばれる馬の胴体に巻く泥よけの馬具に似ることによる。
ハワイ以西の西太平洋からインド洋の熱帯・温帯域に広く分布する。日本では北海道以南の沿岸に分布し、特に太平洋側では鹿島灘以南、日本海側では福井県の西側以南に多い。
通常は深場に生息するが、春から夏にかけて産卵のため海岸近くの浅場にやってくる。海藻や岩の隙間にマメの鞘のような寒天質の卵鞘を一ヶ所に固めて産卵する。産み付けられた卵が魚に食べられる事は無い。卵鞘の中にバクテリアがいて、魚が嫌がる物質を出していると考えられている。
卵からは20日ほどで孵化し、幼体は浅い海で小魚や甲殻類を捕食して成長する。夏には体長数cmの幼体が浅い海で落ち葉のように擬態し、波間に漂う様が観察できる。幼体は沿岸の浅い海で体長15cm-20cmほどまで成長し、冬になると深場に移動する。
外見がバショウの葉に似ることからバショウイカとも呼ばれる。その他藻場に産卵するため四国地方ではモイカ、九州地方ではミズイカ、クツイカ、沖縄地方ではシロイカ(シルイチャー)などの別名がある。』
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
アオリイカ釣り専門サイト「あおりパラダイス」
アオリイカの捌き方
アオリイカ天ぷらレシピ
アオリイカの糸作りレシピ
イカのぬたレシピ


30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
大きさ:40cm
学名:Sepioteuthis lessoniana 英名:Big fin reef squid
地方名:ミズイカ、モイカ、バショウイカ
軟体動物門-頭足綱-ツツイカ目-ヤリイカ科
分布:北海道南部以南の各地、インド・西太平洋の温・熱帯域
<特徴>
『胴長は約40-45cm。大きいものでは50cm以上、重さは6kg以上に達する。沿岸域に生息するイカとしては大型の部類に入る。
胴が丸みを帯び、胴の縁に渡って半円形のひれを持つ。外見はコウイカに似るが、甲は薄くて透明な軟甲である。雄の背中には白色の短い横線模様が散在するが、雌は横線模様が不明瞭である。
標準和名のアオリイカは漢字では障泥烏賊と書くが、この名前はひれの色や形が障泥(あおり)と呼ばれる馬の胴体に巻く泥よけの馬具に似ることによる。
ハワイ以西の西太平洋からインド洋の熱帯・温帯域に広く分布する。日本では北海道以南の沿岸に分布し、特に太平洋側では鹿島灘以南、日本海側では福井県の西側以南に多い。
通常は深場に生息するが、春から夏にかけて産卵のため海岸近くの浅場にやってくる。海藻や岩の隙間にマメの鞘のような寒天質の卵鞘を一ヶ所に固めて産卵する。産み付けられた卵が魚に食べられる事は無い。卵鞘の中にバクテリアがいて、魚が嫌がる物質を出していると考えられている。
卵からは20日ほどで孵化し、幼体は浅い海で小魚や甲殻類を捕食して成長する。夏には体長数cmの幼体が浅い海で落ち葉のように擬態し、波間に漂う様が観察できる。幼体は沿岸の浅い海で体長15cm-20cmほどまで成長し、冬になると深場に移動する。
外見がバショウの葉に似ることからバショウイカとも呼ばれる。その他藻場に産卵するため四国地方ではモイカ、九州地方ではミズイカ、クツイカ、沖縄地方ではシロイカ(シルイチャー)などの別名がある。』
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
アオリイカ釣り専門サイト「あおりパラダイス」
アオリイカの捌き方
アオリイカ天ぷらレシピ
アオリイカの糸作りレシピ
イカのぬたレシピ
2009年06月19日
魚名:アオヤガラ
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より
大きさ:1.5m
学名:Fistularia commersonii 英名:Cornet fish
地方名:フエフキ、ヤガラ
脊椎動物門-硬骨魚綱-トゲウオ目-ヤガラ科
分布:本州中部以南、インド・太平洋
<特徴>
尾柄部にある側線鱗に鋭い後向きのトゲがないことでアカヤガラと区別する。やや浅めの岩礁やサンゴ礁に生息している。状況により体色が変化し、ふだんは青みがかったオリーブ色か淡い褐色であるが、興奮すると暗めの褐色の幅広い横帯が現れる。長く突き出た口を使って小動物を吸い込んで食べる。食用となるがアカヤガラほどおいしくない。 (デジタルお魚図鑑より)
更に、「珍食材図鑑 日本全国の希少食材」では下記のような特徴をあげています。
『日本産ヤガラ科はアカヤガラとアオヤガラの2種(世界でも4種しかいないが…)いる。筒状の長大な吻が特徴で、体も細長い棒状で、尾鰭の中央が長く糸状にのびる。アカヤガラの体色は名の通り赤みがあり、アオヤガラの体色は青っぽいことが多いが、体色には変異があり、見分けにくい場合もある。
アオヤガラは生時、体全体に幅の広い暗色横帯が出たり、消えたりするので、これを覚えておくと見分けやすい。あとアカヤガラの尾柄部の側線鱗には後ろ向きの鋭い棘があり、アオヤガラにはない。両眼の間がアカヤガラは深くへこんでいて、アオヤガラは平たい。
なぜ、アカヤガラとアオヤガラの見分けを、しつこく書いたかというと、食味がまったく違う。アカヤガラは高級料亭でも食材に使われるほど美味しい。夏が旬で、淡泊な白身は、いろいろな料理にあう。めったに釣れないが釣れたら喜ぼう。アオヤガラは、身に臭みがあり、食べられないことはないが、あまり喜ばれない。
ヤガラとは矢柄と書き、矢の柄のことだ。超細長くて最大2メーターくらいになる肉食魚で、小魚を筒のような口で吸いこんでしまう、けったいな奴。しかし美味しくて喜ばれ、吻部や頭部は乾燥させて漢方薬としても珍重された。』
また、「市場魚貝類図鑑」では下記のようなコメントがしてあります。
『アカヤガラと比べると小型のようで、市場に紛れ込んでいるのも50~60センチ前後。身はほとんどない。大きいものはうまい。刺身にして旨味は少ないけど、身質がいい。昆布締めなどにしてうまい。
小型のものは仕方なくみそ汁に入れたり、頭を落として干物にする。塩焼き、干物は美味だし、煮つけみそ汁も決して味は悪くない。』


HONDEX(ホンデックス) HE-51C
【ニューモデル】魚の反応を安易に判別。フィッシュアラームとフィッシュマークのお知らせ機能付き。海底の硬さを安易に判別。底質レベルを数値とグラフで表示。海底付近に近づいてクローズアップ。2倍4倍8倍の拡大表示機能搭載。バッテリー不要。電池BOX内蔵で最大10H駆動可能。コンパクトに収納。架台兼前面保護カバー付き。らくらく&気軽に持ち運び。ストラップ付き。
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より
大きさ:1.5m
学名:Fistularia commersonii 英名:Cornet fish
地方名:フエフキ、ヤガラ
脊椎動物門-硬骨魚綱-トゲウオ目-ヤガラ科
分布:本州中部以南、インド・太平洋
<特徴>
尾柄部にある側線鱗に鋭い後向きのトゲがないことでアカヤガラと区別する。やや浅めの岩礁やサンゴ礁に生息している。状況により体色が変化し、ふだんは青みがかったオリーブ色か淡い褐色であるが、興奮すると暗めの褐色の幅広い横帯が現れる。長く突き出た口を使って小動物を吸い込んで食べる。食用となるがアカヤガラほどおいしくない。 (デジタルお魚図鑑より)
更に、「珍食材図鑑 日本全国の希少食材」では下記のような特徴をあげています。
『日本産ヤガラ科はアカヤガラとアオヤガラの2種(世界でも4種しかいないが…)いる。筒状の長大な吻が特徴で、体も細長い棒状で、尾鰭の中央が長く糸状にのびる。アカヤガラの体色は名の通り赤みがあり、アオヤガラの体色は青っぽいことが多いが、体色には変異があり、見分けにくい場合もある。
アオヤガラは生時、体全体に幅の広い暗色横帯が出たり、消えたりするので、これを覚えておくと見分けやすい。あとアカヤガラの尾柄部の側線鱗には後ろ向きの鋭い棘があり、アオヤガラにはない。両眼の間がアカヤガラは深くへこんでいて、アオヤガラは平たい。
なぜ、アカヤガラとアオヤガラの見分けを、しつこく書いたかというと、食味がまったく違う。アカヤガラは高級料亭でも食材に使われるほど美味しい。夏が旬で、淡泊な白身は、いろいろな料理にあう。めったに釣れないが釣れたら喜ぼう。アオヤガラは、身に臭みがあり、食べられないことはないが、あまり喜ばれない。
ヤガラとは矢柄と書き、矢の柄のことだ。超細長くて最大2メーターくらいになる肉食魚で、小魚を筒のような口で吸いこんでしまう、けったいな奴。しかし美味しくて喜ばれ、吻部や頭部は乾燥させて漢方薬としても珍重された。』
また、「市場魚貝類図鑑」では下記のようなコメントがしてあります。
『アカヤガラと比べると小型のようで、市場に紛れ込んでいるのも50~60センチ前後。身はほとんどない。大きいものはうまい。刺身にして旨味は少ないけど、身質がいい。昆布締めなどにしてうまい。
小型のものは仕方なくみそ汁に入れたり、頭を落として干物にする。塩焼き、干物は美味だし、煮つけみそ汁も決して味は悪くない。』


HONDEX(ホンデックス) HE-51C
【ニューモデル】魚の反応を安易に判別。フィッシュアラームとフィッシュマークのお知らせ機能付き。海底の硬さを安易に判別。底質レベルを数値とグラフで表示。海底付近に近づいてクローズアップ。2倍4倍8倍の拡大表示機能搭載。バッテリー不要。電池BOX内蔵で最大10H駆動可能。コンパクトに収納。架台兼前面保護カバー付き。らくらく&気軽に持ち運び。ストラップ付き。
2009年06月18日
魚名:アオミシマ

デジタルお魚図鑑より
大きさ:40cm
学名:Xenocephalus elongatus 英名:Blue spotted stagazer
地方名:アカサンボ、ムシマ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ミシマオコゼ科
分布:北海道以南、東シナ海、渤海 大きさ:40cm
正直なところ、アオミシマなんて魚の名前を知ったのは今回が初めてです。これまでに見たことも、釣ったことも、また食べたこともありませんでした。
世間でもそれほど知られていないようで、それほど多くの話題は見出せませんでした。
<特徴 >
頭と体は縦に平たく、尾の部分は丸い。頭部側面の上部にやや大きな目がある。背びれは1つ。成長とともに下あごが張り出す。胸びれは四角形である。産卵期は8~10月で夏~秋に黒いフグのような稚魚が沿岸で見ることができ、成長しながら大陸棚の斜面に降りていく。1年で7cm、3年で24cm、5年で35cmに成長する。
「水族館ふりーく」と言うサイトでは下記のような記述がありました。
『まだまだ幼魚なので数cm程度の小さな個体ですが、30cm程度にまで成長する魚です。成長するとどんどん下顎が出てきて、面白い顔になってきます。(笑)
味はよくないとされ、雑魚として扱われ練り製品の原料となっているくらいです。まあ、人間からはあまり相手にされない魚のようですが…個人的にはアオミシマは大変貪欲な魚という印象があります。
というのもこの水槽に同居していたお魚さんたち、ほとんどが彼の胃袋に納められてしまったとのことです。また、底曳網でしばしば漁獲がある魚なのだそうですが、水揚げされるときは大抵何かをくわえているそうです…(^^;』
更に、「市場魚介類図鑑」さんでは下記のように言っておられます。
『一般には流通しない。水揚げの港でも雑魚として扱われる。安い。日本各地から東シナ海、黄海。定置網や浅い場所を曳く底引き網でとれるもの。
あまりうまいとは言えない魚であるが、やや赤みがかった白身で工夫次第でいろいろ使えそうだ。刺身、煮つけや、ブイヤベースの材料ともなる。』
2009年06月17日
魚名:アオブダイ

デジタルお魚図鑑より
大きさ:80cm
学名:Scarus ovifrons 英名:Blue humphead parrotfish
地方名:アオ、バンド
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ブダイ科
分布:東京湾~フィリピン

<特徴>
『名のとおり体色は青みが強いが、体の各所に赤褐色、白、黒などの斑点が出るものもいる。成魚は頬に白っぽい斑点が出て、前頭部がこぶのように突き出るが、若魚は頬に斑点がなく、額にこぶもない。
上下の顎の歯が融合して、鳥のくちばしのような形状をしている。これは他のアオブダイ亜科の魚にも共通する特徴で、人間の指を噛み切るくらいの顎の力もあるので注意が必要である。
東京湾、朝鮮半島以南からフィリピンまでの西太平洋に分布し、浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息する。ナンヨウブダイやカンムリブダイなど、他のアオブダイ亜科の魚が熱帯のサンゴ礁に生息するのに対し、アオブダイは温帯域にも生息する。
食性は雑食性で、藻類、甲殻類、貝類などいろいろなものを食べる。強靭な歯と顎でサンゴの骨格をかじるとされてきたが、これはサンゴではなく、サンゴの枝についた藻類を食べるための行動とみられる。現在のところ、生きたサンゴを餌にするのが確認されたのはアオブダイに近縁のカンムリブダイ Bolbometopon muricatumだけである。
昼間に活動し、夜は岩陰などで眠る。眠る際は口から粘液を出して、自分を覆う薄い透明の「寝袋」を作り、その中で眠る行動が知られている。
釣りや網などで漁獲され、食用になる。ただしアオブダイを狙って釣る人は少なく、イシダイやメジナの釣りで混じって釣り上がり、「外道」として扱われることが多い。
また、特徴的な魚だけに、古来から各地方独特の方言呼称もある。』
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
<食中毒>
日本では過去に数件、アオブダイによる食中毒での死亡例があるそうです。アオブダイはスナギンチャクを捕食するためパリトキシンという強力な毒成分を蓄えており、内臓を食べてはいけないとされています。
また、フグ毒で知られるテトロドトキシンが内臓から検出された事例もあるとのことです。 なお、パリトキシンは加熱や塩蔵によっては分解されないそうです。
日本最大級!世界のグルメ・海の幸をお取り寄せ

2009年06月16日
アオハタの食べ方
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


デジタルお魚図鑑より

アオハタの料理としては刺身、握り、蒸し、煮付け、鍋、焼き、何でもいけるようです。中華でも姿蒸し、清蒸全魚が超高級な料理として評価が高いそうです。また、ムニエル、グリルなどにも向くようです。
アオハタの刺身は程よく脂が乗った上品な白身で、ポン酢がよく合うようです。モミジオロシ、刻み葱などと一緒に食べると美味いとのことです。
またイタリア料理風に、カルパッチョにしては、塩とレモン汁とペッパーのみで、身に弾力があり、ほんのりと上品な甘みがして美味しいそうです。
さて、「アオハタのかぶと蒸し」を紹介されているサイトがありましたので、こちら(「筋肉料理人の料理トレーニング2」)をご覧ください。
「RobotFX」+「システムトレード対応」+「メタトレーダー採用」


30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

デジタルお魚図鑑より

アオハタの料理としては刺身、握り、蒸し、煮付け、鍋、焼き、何でもいけるようです。中華でも姿蒸し、清蒸全魚が超高級な料理として評価が高いそうです。また、ムニエル、グリルなどにも向くようです。
アオハタの刺身は程よく脂が乗った上品な白身で、ポン酢がよく合うようです。モミジオロシ、刻み葱などと一緒に食べると美味いとのことです。
またイタリア料理風に、カルパッチョにしては、塩とレモン汁とペッパーのみで、身に弾力があり、ほんのりと上品な甘みがして美味しいそうです。
さて、「アオハタのかぶと蒸し」を紹介されているサイトがありましたので、こちら(「筋肉料理人の料理トレーニング2」)をご覧ください。
「RobotFX」+「システムトレード対応」+「メタトレーダー採用」

2009年06月15日
魚名:アオハタ

デジタルお魚図鑑より
大きさ:30cm
学名:Epinephelus awoara 英名:Banded grouper
地方名:アオナシモウオ、タカバ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ハタ科
分布:南日本~南シナ海

<特徴>
沿岸の浅めの岩礁域や砂泥底域に生息する。特に日本海沿岸の宮津や舞鶴でよく漁獲される。沿岸魚としては相当おいしい。体側に幅広い5本の暗色横帯があり、そのうち前方にある4本は対に並んでいる。コクテンアオハタに似るが横帯の周囲に黒点がないことで区別できる。
このアオハタについては、「東京のさかな」の中で下記のように紹介されています。
『東京の市場では非常に登場回数が多い。主に北陸から山口までの日本海側、九州などから入荷してくる。白身魚として関東でもじょじょに認識されていっている。
ハタ科であることから値段も安定している。最近では近縁の「あこう」キジハタよりも入荷頻度が多いのではないか?
このアオハタを始め小振りのマハタ属は関西ではハモと並び称されるもので夏の魚として珍重される。たぶんキジハタとともに関西では高級魚としてしっかり認知されているはずだ。本来、関東では扱わなかったのが関西料理の台頭で利用されてきたものだと思う。
またキジハタはある程度、種を認識されているが、こちらは種名などあまり知られていない。地方によっては色合いから「黄」がつく呼び名が多いので、惑わされるようだ。』
また、味わいは良く、非常においしい魚だそうです。しかし、クエのようには大きくならず、ハタ科の中では小さい部類で2~3kg程度の大きさにしかならないようです。
また、価格面でもクエ等と比較するとかなりリーズナブルだそうですが、ただ、ハタ科の中ではリーズナブルって言うだけで高級魚の価格だそうです。

腰痛の予防解消 突然のぎっくり腰に最適
医師が考案した「お医者さんのコルセット」
着けるだけで無理なく姿勢を正し、腰痛や背中の痛みを予防、
元気よく歩き回ることができるようになります
2009年06月14日
アオダイの食べ方

アオダイについては昨日、東京の市場では高級魚として知られていると言いましたが、その所為でしょうか、一般の私達の家庭の食卓には殆ど上らないようです。
で、そのアオダイの食べ方に関しては、「市場魚介類図鑑」で下記のように紹介されていました。
『刺身は非常に美味。当然カルパッチョにもいい。
寿司ネタとしても使われるクセのない魚。
また、八丈島をはじめ伊豆七島に島ずし(正しい呼び名があるのかも知れない)というのがある。しょうゆとみりん(砂糖)などのたれに漬け込んで、握り寿司のネタとするのであるが、淡白なアオダイの味わいにはしょうゆの旨味が合う。
白身でクセがない魚はどこか旨味に欠けるのを、こうすればより一層うまく食べることができる。この島寿司の場合、わさびではなく辛子を薬味にする。
また塩焼き、中華風蒸しもの、フライ、ムニエルと料理の幅はすこぶる広い。』
また、「アオダイの湯びき」について、こちらのサイトで下記のように解説されていました。
『名前のとおり、釣り上げたときほれぼれとするほど美しい魚で、これは皮を湯引きして「松皮造り」にした。魚の旨味は身と皮の間に詰まっているので、それを味わう1品だ。
あらかじめボウルなど大きな容器に氷水を用意しておく。次に、傾けたまな板に片身を、皮を表に、尾側を上にして並べる。
その皮に熱湯をゆっくりかけていく(このとき片身をペーパータオルか布巾で覆って、 その上から熱湯をかけるのが本来のやり方だと、細山さんは言っていた)。
皮が丸まってきたら氷水に入れて身を引き締め、粗熱が取れたら水気を拭き、小骨を取る。』
その、「湯びき」の方法が下記の動画で見られます。
おやじ流手料理
おもちゃステーション「ビッグビィ」

2009年06月13日
魚名:アオダイ

(「デジタルお魚図鑑」より)
大きさ:50cm
学名:Paracaesio caerulea 英名:Blue fusiliner
地方名:アオゼ、ウメイロ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-フエダイ科

<形態>
体色は一様に青紫色で腹部は淡色。体側に横帯がない。体は長円形で側扁し、背ビレと臀ビレの軟条には鱗がない。背ビレには欠刻がない。尾ビレは二叉する。眼隔域が隆起し、胸ビレは鎌状で長い。体長40cm以上に達する。
<分布>
日本列島周辺にのみ生息が知られ、主として南日本に分布する。東京の海域では神津島から小笠原にかけて生息するが、分布の中心は八丈島近海である。
アオダイ属の魚種は、ヨゴレアオダイ Paracaesio sordida Abeが伊豆・小笠原諸島海域から、シマアオダイ Paracaesio kusakarii Abeが鳥島海域から採集されているが、その個体数は少ない。
<生態>
水深100m以深の岩礁域に生息する。肉食性で魚類、甲殻類を捕食し、産卵期は6月から9月である。満3年で産卵が始まり、直径0.8mm前後の球形の浮性卵を産出する。
小笠原では、西の島での採集例があるが、いずれも尾叉長40cm以上の大型個体で若齢魚の採集記録はない。
(「東京都島しょ農林水産総合センター」より)
市場関係者によりますと、東京の市場では高級魚として知られているようで、都内・伊豆七島、小笠原からの入荷が多く、正真正銘の「東京の魚」だそうです。
旬は夏から秋、初冬にかけてだそうです。市場に入荷するのは量的には普通だが、入荷頻度は高いとのことです。
価格については、東京では高級魚として一定の評価を得ているので、最低でもキロあたり1500円前後、一番多い価格帯は2000円前後、ときに3000円を超えることもあるそうです。
ただ、この魚は一般的ではないので、普通の家庭などでは使われいないようです。ですから、スーパーではまず売られていないらしいです。どうしても、料理屋、やや高いが魚屋などで時に扱うものとのことです。
(「市場魚貝類図鑑」の記述参照)
2009年06月12日
アオザメの食べ方

普段、アオザメなどにはお目にかかりませんので、食べたことがある方は少ないのではないでしょうか。関東の市場では非常に希だそうですが、広島県芸北地方(この地方では、「わに」と言っているそうです)では普通に食べられているとのことです。値段は安いようです。
一般にサメは、蒲鉾などのねり物に利用されることは知っていますが、フカひれなどにも利用されるようです。また、フライ/干物(たれ、鉄干し)にもされるようです。ちょっと食べるのに勇気が要りますが、刺身にすると淡白で旨味が薄いけれども、食べやすいとのことです。
尚、外国でもヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなどではサメをよく食するようです。中でもイタリアではステーキとしても賞味されているそうです。
ところで、サメの食べ方については、こちらのサイトで下記のように記述されていました。
『サメの食べ方としては、鮮度のよいものであれば刺身、湯引き、大概は煮付け、焼き物です。ほかの魚となんらかわったところはありません。臭い消しに酢味噌で食べることも多いです。
変わった食べ方として、当社で製品化している「すくめ」「なます」があります。
頭などを煮てほぐし、冷やすとにこごりができます。大根おろし、酢味噌、刻みねぎで食べます。お正月に良く食べます。
サメを使った皆さんに身近な商品をあげさせていただきます。九州のさつま揚げは大変有名です。あれはもともとサメ肉のみを使用したそうです。
いまでも高級なものはアオザメを使用するとのこと。また、ハンペン、高級チクワ、各種練り製品の原料になっていることはご存知の方も多いと思います。神奈川のおでんの具「スジ」。これが実はサメなのです。』
また、色々なサメ料理についても、こちらで紹介されていました。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tamukai/sameryouri.htm

2009年06月12日
魚名:アオザメ

( 「デジタルお魚図鑑」 より)
大きさ:4m
学名:Isurus oxyrinchus 英名:Atlantic mako
地方名:アオ、アオヤギ、イラギ
脊椎動物門-軟骨魚綱-ネズミザメ目-ネズミザメ科
分布:温帯から熱帯にかけての外洋域 大きさ:4m

<特徴>
『サメ類の中で最速の部類に入り、18ノット(時速35km)以上の速さで泳ぐことが出来るといわれている。この高速遊泳を可能にするため、アオザメはいくつかの生態的・形態的特徴を持っている。
最も大きな特徴は、奇網という毛細静脈と毛細動脈が緻密に入り組んだ熱交換システムを筋肉の近傍に備えており、体温を周囲の海水温よりも高く保つことができることである。
人間でも、例えば冬の寒い戸外にいて体温が低いときよりも、風呂に入ったりして体温が高いときの方が筋肉の運動性が良くなる。これと同じようにアオザメは奇網により体温、中でも筋肉の温度を高く維持しておくことで、たとえ冷たい海水中でも筋肉の運動性を低下させないようにしている。
このような仕組みは高速遊泳を行うマグロ類やカジキ類などにも見られる。また海中から空中に高速で飛び出すことにより、高くジャンプすることが出来る。
体は流線型で、水の抵抗を受けにくい。 尾鰭はほぼ三日月型で、長時間の回遊と爆発的遊泳に適した形である。
また、歯は三角形で鋭く、海産哺乳類など大型の獲物を捕らえて食いちぎるのに便利である。 おそらく捕食の際には、高速で獲物に襲いかかり、強力な顎と歯で致命傷を負わせるものと考えられ、アオザメが有能なハンターであることをうかがわせる。』
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
ところで、アオザメは釣ったときの引きが強く、ジャンプするため、欧米ではスポーツフィッシングの対象になっているそうです。ちょうど、アオザメを釣っている動画がありましたので紹介します。(「サメ動画集」より)
http://sharkfan.net/cat44/cat29/