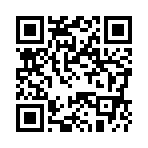2009年06月11日
アイブリの食べ方

アイブリの食べ方については、あまり知られていない魚なので、これと言った特別の方法は見つかりません。他のアジ科の魚と比べると身が柔らかく白くにごって透明感がないそうですが、刺身にすると味はよくて旨味、甘みとも充分にあるそうです。また煮つけや塩焼きも上々とのことです。
この他にも、粕漬け、タマリ漬けなどにして食べる方もあるようです。
尚、寿司で食べることについて、「市場魚貝類図鑑」の中で下記のように記述されています。
『晩秋の沼津魚市場、巻き網船が入港してきている。大量のアカカマス、ゴマサバ、さごし(サワラ)、マルソウダ。カマスは値がつくから今日は大漁だ! なんて、ふと選別台の下を見るとアイブリが落ちている。
「もらっていいかな」と言うと、「こっちにもあるから」と2本、3本。「うまいだらけんど、競りに出しても値がつかないだら」と船から声がかかる。それを持ち帰ってすぐ「市場寿司 たか」へ。
「まるでカンパチの子みたいだね」。お卸し始めると「あれー? 身の色が違うぞ。メダイに似てる」。たかさん久しぶりに魚らしい魚でちょっと喜んでいるみたいだ。
そして2かん。これが「平凡だけど、味のいい握り」なのである。まさにメダイの握りに近い。メダイと違うのは、ほんの微かに酸味があって、でもそれを補うように甘味も感じられる。
「オレはこれ好きだね」、たかさん、寿司ネタとして気に入ったようだ。「また沼津に行ったらたのむよ」。』
ところで、タイ料理では、アイブリをよく食べているようですよ。下記のように紹介されていました。
(「Thai Food & Restarurants Guidehttp」 より)
『アイブリの醤油蒸し
イシモチに似たこの魚は、英語料理名では『Cotton Fish』と呼ばれ、タイでは食材としてよく使われます。白身の魚で、脂ののりはさほど良くなさそうなので、こうした蒸し煮にするよりも、揚げ魚(トーッ・ラーッ・プリックもしくはトーッ・サームロットなどのしっかりしたソース掛け)にした方が良いような気がします。タイ人って揚げ魚が大好きなんですよね。』

2009年06月11日
魚名:アイブリ


大きさ:70cm
学名:Seriolina nigrofasciata 英名:Black-banded amberjack
地方名:シホノオバサン、ハマチ
脊椎動物門?硬骨魚綱?スズキ目?アジ科
分布:南日本、インド・西太平洋
私は、この魚の名前を知ったのは初めてです。釣ったことも、食べたこともありませんので、一体どんな魚のか興味があり、ここに取り上げました。取り敢えず、調べたところを紹介します。
<特徴>
体形はカンパチ、模様はブリモドキに似ている。南日本、暖流の影響の強い地域によく見られる。幼魚では斜めに走る横縞が目立つが大きくなると消えてしまう。
定置網、巻き網などでぽつんと1匹から数匹とれることが多く、どうも群れを作らないようだ。
関東の市場では入り会い(数種類の魚を1箱に入れて出荷する)でまれに見ることが出来る。産地では地元用に出回るもので、まとまらないために出荷できないことが多いためか値段がつかないか、非常に安い。
当然、市場での値段も安いので、「うまい魚」であることがわかっていればお買い得。産地でもある程度の大きさで、まとまれば出荷して欲しい。(「市場魚貝類図鑑」 http://www.zukan-bouz.com/aji/tumuburi/aiburi.html より)

2009年06月10日
アイナメの話題


アイナメに関する下記のような面白い記事がありました。(「ミニコミ明石」より)
『最近、地元明石の海で私が撮影するのにストーカーのようになっている魚がいる。それはアイナメである。「えっアイナメ?」と思う方もいるだろう。
なぜなら、浅い岩礁域に住みこの辺りの海だとどこにでもいる釣り人に人気はあるものの、見かけも普通の魚だからだ。
では、なぜ何の取柄もなさそうな魚を追っかけてるかというとダイバーにしか見ることができないおもしろい繁殖行動をとるからである。
アイナメのオスは潮通しの良い場所に縄張りを持ち、秋~冬にかけてメスに求愛行動をする。その時のオスの体色は少し、オレンジが強くなったような感じになる。
そして縄張りにメスを誘い込み、イクラより少し小さいぐらいの卵を産ませる。そしてオスはその卵を食べに来る他のアイナメや、魚から卵を守る。
アイナメにとって他のアイナメの卵は大好物なのだが、自分の子供の卵は食べないのだから親の愛を感じる。
卵の孵化までは約1ヶ月なのだが、単純に一ヶ月卵を守るだけではない。正確に言うと一匹の奥さんだけだと、一ヶ月でいいんだが、実はアイナメは繁殖シーズン中は、次から次へと自分の縄張りにメスを呼び込み、卵を産ませる。
だから、産み付けられた卵を見るとオレンジがかった卵から既に目が見える卵まで様々である。ということは、もてるアイナメは繁殖シーズン中はずっと卵を守っているわけである。
魚は自分の子孫を残すということを一番に考える遺伝子なので、そんな一夫多妻制みたいな繁殖行動をとるが、人間だとただのスケコマシである。
明石での卵を守ってるアイナメの探し方は簡単で、単純に逃げないアイナメを見つけ、その回りを探すと卵が見つかる。現在は卵から孵化する瞬間を撮影したく、極寒の瀬戸内海、明石の海で奮闘中です!』
他に、YouTubeの動画で、釣り人がアイナメの刺身を造っているのがありましたので紹介します。
アイナメの刺身

タグ :明石
2009年06月09日
アイナメの食べ方
アイナメは、刺身・煮つけ・唐揚げ・天婦羅・焼き物などと、料理の方法が多い魚です。私は煮付けも好きですが、唐揚げが一番好きです。それに大根おろしを添えて食するのが最高です。
「アイナメのさばき方、下処理」はこちらを参考に!
変わったところでは、下記のような「皮の湯びき」とか「皮霜造り」などの料理法を紹介されている方があります。

(1)皮の湯引き
<材料>
刺身を造った残りの皮・適量。
<作り方>
1,皮をまな板の上に並べ、沸騰したお湯をかける。すぐに用意しておいた氷水に入れ、粗熱を取る。
2,5mm~1cm幅に刻む。酢味噌、あるいは辛子巣味噌で賞味する。
<注意点>
アイナメは皮が美味い魚です。引いた皮は絶対に捨てないこと。これだけで立派な一品が仕上がります。皮を美味しく食べるためには、ウロコはていねいに取ること。アイナメのウロコは細かくて引くのに苦労しますが、ウロコ引きで落とした後、大根の輪切りで逆なでするときれいに取れるそうです。
(2)アイナメの皮霜造り
<材料>
アイナメ(25cm以上)・1匹。
<作り方>
1,アイナメを三枚におろし、血合い骨をていねいに抜き取る。
2,皮を上にしてまな板の上に並べ、固く絞った濡れ布巾をかぶせ、熱湯をサッとかける。
3,すぐに用意しておいた氷水に入れて粗熱を取る。
4,1cm幅の平造りにし、ワサビ醤油で賞味する。
<注意点>
必ず、氷水はあらかじめ用意しておくこと。熱湯をかけたら、瞬時に氷水へ入れること。ボヤボヤしていると身が煮えてしまう。1cm幅の平造りにして、酢の物かヌタにしてもよいそうです。
こちらで、アイナメの料理について解説されています。

「アイナメのさばき方、下処理」はこちらを参考に!
変わったところでは、下記のような「皮の湯びき」とか「皮霜造り」などの料理法を紹介されている方があります。

(1)皮の湯引き
<材料>
刺身を造った残りの皮・適量。
<作り方>
1,皮をまな板の上に並べ、沸騰したお湯をかける。すぐに用意しておいた氷水に入れ、粗熱を取る。
2,5mm~1cm幅に刻む。酢味噌、あるいは辛子巣味噌で賞味する。
<注意点>
アイナメは皮が美味い魚です。引いた皮は絶対に捨てないこと。これだけで立派な一品が仕上がります。皮を美味しく食べるためには、ウロコはていねいに取ること。アイナメのウロコは細かくて引くのに苦労しますが、ウロコ引きで落とした後、大根の輪切りで逆なでするときれいに取れるそうです。
(2)アイナメの皮霜造り
<材料>
アイナメ(25cm以上)・1匹。
<作り方>
1,アイナメを三枚におろし、血合い骨をていねいに抜き取る。
2,皮を上にしてまな板の上に並べ、固く絞った濡れ布巾をかぶせ、熱湯をサッとかける。
3,すぐに用意しておいた氷水に入れて粗熱を取る。
4,1cm幅の平造りにし、ワサビ醤油で賞味する。
<注意点>
必ず、氷水はあらかじめ用意しておくこと。熱湯をかけたら、瞬時に氷水へ入れること。ボヤボヤしていると身が煮えてしまう。1cm幅の平造りにして、酢の物かヌタにしてもよいそうです。
こちらで、アイナメの料理について解説されています。

2009年06月09日
魚名:アイナメ

大きさ:30cm
学名:Hexagrammos otakii 英名:Fat greenling
地方名:アブラメ、クロテン
脊椎動物門-硬骨魚綱-カサゴ目-アイナメ科

アイナメの語源には、アユのように滑らかなので「アユナメ(鮎滑)」が転じたとする説と、アユに似ていることから、「アユナミ(鮎並)」が転じて「アイナメ」になったとする説があるそうです。
<特徴 >
全長30cm-40cmほどだが、60cmを超えるものもいる。カサゴ、メバル、カジカなどと同じカサゴ目に分類されるが、アイナメはひれの棘条(とげ)が発達しないこと、背びれが1つに繋がっていること、体高が高いこと、鱗が細かいことなどが特徴である。これらの特徴はクジメやホッケなど、他のアイナメ科の魚にも共通する。
体色は生息地の環境により黄、赤褐色、紫褐色など様々だが、繁殖期のオスには黄色の婚姻色が現れる。近縁種のクジメとは尾びれが三角形に角ばっていることで区別できる。
また、アイナメの側線は体側中央だけでなく背びれ、腹びれ、尻びれの根もとに計5本もあるが、クジメの側線は体側の1本だけである。
南西諸島と太平洋側の一部を除く日本各地の沿岸に生息し、日本以外では朝鮮半島と黄海沿岸にも分布する。昼行性で、岩礁帯やテトラポッド、防波堤などの陰につき、小魚や甲殻類、多毛類などを捕食する。
産卵期は秋から冬で、オスは岩陰などにメスを誘い込み産卵させる。オスは巣に次々と複数のメスを誘い込んで産卵させるので、卵は緑褐色や赤紫色の大きな卵塊となる。
産卵が終わった後もオスは卵のそばに残り、敵を追い払って卵塊を守る。孵化した稚魚は岩礁の周辺を泳ぎ回りながら成長するが、全長5cmを超えると親魚と同じように底生生活に移る。(百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

2009年06月08日
アイゴの釣り方、食べ方
<アイゴの釣り方>
積極的に「アイゴ」を釣る所では、ウキ釣り・サビキ釣り・フカセ釣りなどが行われているようです。
アイゴの釣れる場所:沖釣り・堤防釣り・磯釣りなど
アイゴを釣るポイント:足下から水深がある場所。潮通しの良い磯や堤防が良く釣れる。海草が茂った所が好ポイント。
アイゴは群れでいるので釣れだしたら、トゲに十分気をつけて手返しよく釣ること。コマセを絶え間なく撒くこと。

ダイワ(Daiwa) AQW-4500N アクオリア・ネオプレーンウェーダー
干潟でのウェーディングゲームに的を絞って開発された機能満載の専用ウェーダー。素材は保温性と機動性を両立し、ほぼオールシーズン着用可能な4.0mm厚のネオプレーン。ノリなどの海藻が付着した岩の上でも抜群のグリップ力を発揮するフェルトスパイクソール。長時間のゲームでも肩への負担を和らげ、キャストの妨げにならないスーパー3Dメッシュショルダーベルト。
<アイゴの食べ方>
アイゴの食味に付いては、美味いという人と、磯臭くて食べられないという人に分かれるようです。
刺身・塩焼き・てんぷら・干物・稚魚の酢漬け・煮付けなどが主ですが、洗いにして酢味噌で食べるのもいいそうです。また、高知の人の中には、アイゴのたたきを絶賛されている方もあります。
アイゴの注意点:シリビレ・腹ビレ・背びれなどの各ヒレ部に毒線があり刺されるとかなり痛む。釣れたアイゴを釣針から外すときや料理をする時には細心の注意を払うこと。(死後でも毒があるので要注意)
〇 こちらのサイトで、アイゴ料理が紹介されています。
釣具業界最大!!

積極的に「アイゴ」を釣る所では、ウキ釣り・サビキ釣り・フカセ釣りなどが行われているようです。
アイゴの釣れる場所:沖釣り・堤防釣り・磯釣りなど
アイゴを釣るポイント:足下から水深がある場所。潮通しの良い磯や堤防が良く釣れる。海草が茂った所が好ポイント。
アイゴは群れでいるので釣れだしたら、トゲに十分気をつけて手返しよく釣ること。コマセを絶え間なく撒くこと。

ダイワ(Daiwa) AQW-4500N アクオリア・ネオプレーンウェーダー
干潟でのウェーディングゲームに的を絞って開発された機能満載の専用ウェーダー。素材は保温性と機動性を両立し、ほぼオールシーズン着用可能な4.0mm厚のネオプレーン。ノリなどの海藻が付着した岩の上でも抜群のグリップ力を発揮するフェルトスパイクソール。長時間のゲームでも肩への負担を和らげ、キャストの妨げにならないスーパー3Dメッシュショルダーベルト。
<アイゴの食べ方>
アイゴの食味に付いては、美味いという人と、磯臭くて食べられないという人に分かれるようです。
刺身・塩焼き・てんぷら・干物・稚魚の酢漬け・煮付けなどが主ですが、洗いにして酢味噌で食べるのもいいそうです。また、高知の人の中には、アイゴのたたきを絶賛されている方もあります。
アイゴの注意点:シリビレ・腹ビレ・背びれなどの各ヒレ部に毒線があり刺されるとかなり痛む。釣れたアイゴを釣針から外すときや料理をする時には細心の注意を払うこと。(死後でも毒があるので要注意)
〇 こちらのサイトで、アイゴ料理が紹介されています。
釣具業界最大!!
2009年06月08日
魚名:アイゴ

今回から様々な魚について、あいうえお順に紹介していきます。魚の生態や、釣り方、食べ方などを色々な方面から調べて伝えたいと考えています。
今回は第一回目で、「アイゴ」についてです。釣り師にはどちらかと言うと、外道のように扱われているようですが、土地土地によって、好かれたり嫌われたりと、扱いに違いがあるようです。
大きさ:30cm
学名:Siganus fuscescens 英名:Dusky spinefoot
地方名:アイ、イバリ、バリ、バリコ、アエ
脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アイゴ科
アイゴ釣りの盛んな都道府県:和歌山県・兵庫県・福井県・鳥取県・岡山県・香川県・広島県・徳島県など
琉球諸島を除く本州以南・台湾・オーストラリア西部に分布している。
アイゴの主な生息場所:海藻の多い岩礁やサンゴ礁に生息する。河口などの汽水域にもよく進入する。
<特徴 >
体は楕円形で、極端に平たくなっています。うろこは非常に小さく円鱗(えんりん)で、表面は粘液でぬるぬるし、うろこが無いように見えます。
体は多くは黄褐色で多数の白色班がありますが、個体や棲んでいいる場所によって色が違います。体色を好んですむ海藻帯の色に似せ、保護色・迷彩色にしています。
死後でも物に触れた部分の色が変わります。稚魚は主にけい藻類を、成魚は小動物も食べる雑食性です。各ひれにあるトゲには毒腺があり、刺さると毒液が注入されてヒドイ痛みがあります。