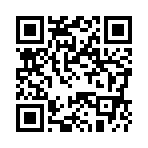2010年07月16日
カタクチイワシ
さかな、サカナ、魚!
(≡^∇^≡) 指圧を受けて見たい、習ってみたいと思われる方は、
=>こちらからご連絡ください!
(≡^∇^≡) 健康・ケンコー・Health
(≡^∇^≡) 雑誌いろいろ、楽しみいろいろ!

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:14cm
学名:Engraulis japonicus
地方名:ヨゴウ、タレッソ、エダレ
脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-カタクチイワシ科
分布:北海道以南、朝鮮半島~南シナ海北部
特徴
成魚の全長は10-20cmほど。体色は背中側が青灰色で、腹側が銀白色をしている。鱗は円形をした「円鱗」(えんりん)だが剥がれやすく、漁獲された際に鱗が脱落してしまうことも多い。断面は背中側がやや膨らんだ卵形をしている。
マイワシ、ウルメイワシと同じくイワシの一種だが、カタクチイワシは目が頭部の前方に寄っていて、口が頭部の下面にあり、目の後ろまで大きく開くことが特徴である。和名も「口が頭の片側に寄っている」ことに由来する。
また、他の2種よりも体が前後に細長い。分類上でも、マイワシとウルメイワシはニシン科(Clupeidae)だが、カタクチイワシはカタクチイワシ科(Engraulidae)である。
北海道から南シナ海までの西太平洋沿岸に分布する。内湾から沖合いまで、沿岸域の海面近くに大きな群れを作る。プランクトン食性で、泳ぎながら口を大きく開けて植物プランクトンや動物プランクトンを海水ごと吸い込み、鰓の鰓耙(さいは)でプランクトンを濾過摂食する。
一方、敵はカモメやカツオドリなどの海鳥、サメやカツオなどの肉食魚、クジラやイルカなどの海生哺乳類、イカ、人間など非常に多岐にわたり、人類の利用のみならず食物連鎖の上でも重要な生物である。
カタクチイワシは天敵から身を守るために密集隊形を作り、群れの構成員全てが同調して同じ向きに泳いで敵の攻撃をかわす。これは他の小魚にも共通する防衛策である。対する敵はイワシの群れに突進を繰り返して群れを散らし、はぐれた個体を襲う戦法を取る。
産卵期はほぼ1年中だが、春と秋に産卵するものが多い。卵は楕円形の分離浮性卵で、1粒ずつがバラバラに水中を漂いながら発生する。孵化した稚魚は急速に成長し、1年経たずに繁殖ができるようになる。寿命は2年-3年ほどである。 (「フリー百科事典ウィキペディア」より)
<カタクチイワシの加工品>
1.煮干し/香川県などで盛んに作られる。ゆでてから乾燥させたもの。年々価格が上がっている。現在では高級品。
2.丸干し/九十九里の目刺し(目に竹串などを通したもの)が有名。
3.ごまめ(五万米)・たづくり(田作り)/カタクチイワシの小さなもの(かえり)を素干しにしたもの。炒って甘辛い地に搦めて正月料理に使う。
4.しらす/稚魚をゆでて上げただけのものを「釜揚げ」、軽く干したものを「しらす干し」。東日本で多い。ちりめん/強く干したものを「ちりめん」。西日本に多い。
5.たたみいわし(畳鰯)/稚魚を水洗いして、すに広げて紙状にして、干したもの。静岡県、神奈川県、茨城県などで作られる。
6.ごま漬け/九十九里などで作られる「ごま漬け」。家庭でも簡単にできる。小型のものを選んで頭と尾を取り、塩をからめ水を抜き水洗い、これを甘酢とごまで漬ける。
7.「みりん干し」、「さくら干し」、「末広干し」/千葉県などで作られている。砂糖しょうゆ、みりん・しょうゆの甘辛いタレに漬けて干したもの。 (「市場魚貝類図鑑」より)
<カタクチイワシの料理>
1.カタクチイワシ おいしいレシピ
2.カタクチイワシの煮付け
3.スペインタパス かたくちイワシのマリネ /a>
4.イワシの竜田揚げシソ風味
5.カタクチイワシの味噌チョリム
6.カタクチイワシのサラダ
<カタクチイワシの動画>
1.小イワシの刺身 小イワシ 簡単レシピ
2.アンチョビの作り方(レシピ)01
3.アンチョビの作り方(レシピ)02
4.アンチョビの作り方(レシピ)03
5.アンチョビの作り方(レシピ)04
6.アンチョビの作り方(レシピ)05
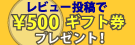
/~\Fujisan.co.jpへ

/~\Fujisan.co.jpへ
(≡^∇^≡) 指圧を受けて見たい、習ってみたいと思われる方は、
=>こちらからご連絡ください!
(≡^∇^≡) 健康・ケンコー・Health
(≡^∇^≡) 雑誌いろいろ、楽しみいろいろ!

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:14cm
学名:Engraulis japonicus
地方名:ヨゴウ、タレッソ、エダレ
脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-カタクチイワシ科
分布:北海道以南、朝鮮半島~南シナ海北部
特徴
成魚の全長は10-20cmほど。体色は背中側が青灰色で、腹側が銀白色をしている。鱗は円形をした「円鱗」(えんりん)だが剥がれやすく、漁獲された際に鱗が脱落してしまうことも多い。断面は背中側がやや膨らんだ卵形をしている。
マイワシ、ウルメイワシと同じくイワシの一種だが、カタクチイワシは目が頭部の前方に寄っていて、口が頭部の下面にあり、目の後ろまで大きく開くことが特徴である。和名も「口が頭の片側に寄っている」ことに由来する。
また、他の2種よりも体が前後に細長い。分類上でも、マイワシとウルメイワシはニシン科(Clupeidae)だが、カタクチイワシはカタクチイワシ科(Engraulidae)である。
北海道から南シナ海までの西太平洋沿岸に分布する。内湾から沖合いまで、沿岸域の海面近くに大きな群れを作る。プランクトン食性で、泳ぎながら口を大きく開けて植物プランクトンや動物プランクトンを海水ごと吸い込み、鰓の鰓耙(さいは)でプランクトンを濾過摂食する。
一方、敵はカモメやカツオドリなどの海鳥、サメやカツオなどの肉食魚、クジラやイルカなどの海生哺乳類、イカ、人間など非常に多岐にわたり、人類の利用のみならず食物連鎖の上でも重要な生物である。
カタクチイワシは天敵から身を守るために密集隊形を作り、群れの構成員全てが同調して同じ向きに泳いで敵の攻撃をかわす。これは他の小魚にも共通する防衛策である。対する敵はイワシの群れに突進を繰り返して群れを散らし、はぐれた個体を襲う戦法を取る。
産卵期はほぼ1年中だが、春と秋に産卵するものが多い。卵は楕円形の分離浮性卵で、1粒ずつがバラバラに水中を漂いながら発生する。孵化した稚魚は急速に成長し、1年経たずに繁殖ができるようになる。寿命は2年-3年ほどである。 (「フリー百科事典ウィキペディア」より)
<カタクチイワシの加工品>
1.煮干し/香川県などで盛んに作られる。ゆでてから乾燥させたもの。年々価格が上がっている。現在では高級品。
2.丸干し/九十九里の目刺し(目に竹串などを通したもの)が有名。
3.ごまめ(五万米)・たづくり(田作り)/カタクチイワシの小さなもの(かえり)を素干しにしたもの。炒って甘辛い地に搦めて正月料理に使う。
4.しらす/稚魚をゆでて上げただけのものを「釜揚げ」、軽く干したものを「しらす干し」。東日本で多い。ちりめん/強く干したものを「ちりめん」。西日本に多い。
5.たたみいわし(畳鰯)/稚魚を水洗いして、すに広げて紙状にして、干したもの。静岡県、神奈川県、茨城県などで作られる。
6.ごま漬け/九十九里などで作られる「ごま漬け」。家庭でも簡単にできる。小型のものを選んで頭と尾を取り、塩をからめ水を抜き水洗い、これを甘酢とごまで漬ける。
7.「みりん干し」、「さくら干し」、「末広干し」/千葉県などで作られている。砂糖しょうゆ、みりん・しょうゆの甘辛いタレに漬けて干したもの。 (「市場魚貝類図鑑」より)
<カタクチイワシの料理>
1.カタクチイワシ おいしいレシピ
2.カタクチイワシの煮付け
3.スペインタパス かたくちイワシのマリネ /a>
4.イワシの竜田揚げシソ風味
5.カタクチイワシの味噌チョリム
6.カタクチイワシのサラダ
<カタクチイワシの動画>
1.小イワシの刺身 小イワシ 簡単レシピ
2.アンチョビの作り方(レシピ)01
3.アンチョビの作り方(レシピ)02
4.アンチョビの作り方(レシピ)03
5.アンチョビの作り方(レシピ)04
6.アンチョビの作り方(レシピ)05
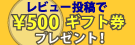
/~\Fujisan.co.jpへ

/~\Fujisan.co.jpへ
Posted by きーさん at 20:19│Comments(0)
│海の魚
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。