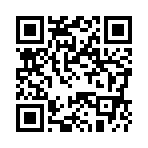2009年08月19日
魚名:イセエビ
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:30cm
学名:Panulirus japonicus 英名:Japanese spiny lobster
地方名:カマクラエビ
節足動物門-甲殻綱-十脚目-イセエビ科
分布:本州中部以南、朝鮮半島南部、台湾
<特徴>
体長は通常20-30cmほどで、まれに40cmに達するものもいる。重さは大きなもので1kg近くになる。体型は太い円筒形で、全身が暗赤色で棘だらけの頑丈な殻におおわれ、触角や歩脚もがっしりしている。エビ類の2対の触角はしなやかに曲がるものが多いが、イセエビ類の第二触角は太く、頑丈な殻におおわれる。
第二触角の根もとには発音器があり、つかまれると関節をギイギイと鳴らし威嚇音を出す。腹部の背側には短い毛の生えた横溝がある。オスメスを比較すると、オスは触角と歩脚が長い。メスは腹肢が大きく、第5脚(一番後ろの歩脚)が小さな鋏脚に変化している。
学名の属名"Panulirus"はヨーロッパ産のイセエビ科 Palinurus 属のアナグラムで、種名"japonicus"は「日本の」の意である。英語では"Spiny lobster"(棘だらけのロブスター)と呼ばれるが、ロブスターはイセエビよりもザリガニに近縁で、エビの分類上では別々に区分される。
硬い甲などの共通点もあるが、イセエビは大きな鋏脚を持たず、長い幼生期(後述)を経る点でロブスターとの差異がある。
<生態>
房総半島以南から台湾までの西太平洋沿岸と九州、朝鮮半島南部の沿岸域に分布する。かつてはインド洋・西太平洋に広く分布するとされたが、研究が進んだ結果他地域のものは別種であることが判明した。
外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息する。昼間は岩棚や岩穴の中にひそみ、夜になると獲物を探す。食性は肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を主に捕食するが、海藻を食べることもある。貝などは頑丈な臼状の大顎で殻を粉砕し中身を食べる。
一方、天敵は人間の他にも沿岸性のサメ、イシダイ、タコなどがいる。敵に遭うと尾を使ってすばやく後方へ飛び退く動作を行う。
繁殖期には他のイセエビの後をついて動くため列を作るという変わった生態がある。
(上記の説明は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
<イセエビの漁法>
イセエビは通常底さし網で捕獲します(イセエビは泳いでいるときに、網目に
しっぽから刺さるか、網にからまるかして捕獲されます)。
夷隅東部漁協のさし網漁は、昼間の1時に網を掛けに行き、翌日の夜中 の2時半に網を揚げに行き、港に戻ってイセエビなどの漁獲物をはずして 市場に出します。これで漁の終了ではなく、そのあとに、網が岩などにす れて切れてしまうので、午前中に網の修繕をします。
網の長さは船の乗組員の人数で決められており、例えば、3人乗りの船で78反 (=約1,950m、1反は約25m)までとなっており、網目も3.1寸 (9.3㎝)以上と決められています。このように、たくさん獲りすぎないように、 また、小さいエビを獲らないように工夫しています。
網を入れる場所は漁獲を左右する最大のポイント! 魚群探知機などで底の形状を見ながら、潮の流れなどを考えて、 根をはずさないように網を入れていきます。まさに長年の経験と最新の科学技術機器を駆使して イセエビを漁獲します。 (「イセエビの生態と漁法」より)
<イセエビの名前の由来>
現代では標準名は「イセエビ」とされていますが、江戸では鎌倉で獲れたものが届くのでカマクラエビ、京や大阪には伊勢から届くのでイセエビと呼ばれていたそうです。
その名前の由来としては諸説あり、例えば、伊勢湾でたくさん獲れたので、伊勢海老になったという説。
磯(いそ)にいるから(いそえび)がなまり、いせえびになったという説。
武士のかぶとの飾りが えびに似ていて 威勢がいいがなまったという説。
伊勢神宮に古くから海老が奉納されていたため、伊勢海老となったいう説。
ひげがピーンとのび威勢のいい海老というところから伊勢海老となったという説。
などなど、どの説ももっともらしいのですが、まことしやかにささやかれているのは、伊勢でたくさん採れたからだそうです。
<イセエビは日本の目出度さのシンボル>
『何が目出度いと言って、伊勢海老ほど目出度いものはありません。あの立派な長いヒゲ、腰を曲げて歩く姿、海の老人は長寿の象徴です。ましてや、武者の甲冑の見本となりそうな、見事な甲羅。もう目出度さの極みです。
と言うことで、正月のお飾りとご馳走、婚儀などあらゆる祝宴、神仏への供物、兜の前立て等々、イセエビの姿なしには日本の祝い事は始まりません。
ただ、際立った姿のために損?をしているのかも知れません。食べる前に味に過大な期待を抱かせてしまうのです。この姿なのだから食べたことがないほどの美味さなのだろうと。
「姿のイセエビ、味のクルマエビ」と言われるのは、味がクルマエビに劣ると言うより、自分の姿に勝てないということのような気がします。美味さは甲乙付けがたい程なのですから。』
(「旬魚余話」より)
☆ イセエビの捌き方
☆ イセエビの動画
☆ 巨大イセエビ
男性だってスキンケア バイオ基礎化粧品b.glen



詳細はこちら>>
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:30cm
学名:Panulirus japonicus 英名:Japanese spiny lobster
地方名:カマクラエビ
節足動物門-甲殻綱-十脚目-イセエビ科
分布:本州中部以南、朝鮮半島南部、台湾
<特徴>
体長は通常20-30cmほどで、まれに40cmに達するものもいる。重さは大きなもので1kg近くになる。体型は太い円筒形で、全身が暗赤色で棘だらけの頑丈な殻におおわれ、触角や歩脚もがっしりしている。エビ類の2対の触角はしなやかに曲がるものが多いが、イセエビ類の第二触角は太く、頑丈な殻におおわれる。
第二触角の根もとには発音器があり、つかまれると関節をギイギイと鳴らし威嚇音を出す。腹部の背側には短い毛の生えた横溝がある。オスメスを比較すると、オスは触角と歩脚が長い。メスは腹肢が大きく、第5脚(一番後ろの歩脚)が小さな鋏脚に変化している。
学名の属名"Panulirus"はヨーロッパ産のイセエビ科 Palinurus 属のアナグラムで、種名"japonicus"は「日本の」の意である。英語では"Spiny lobster"(棘だらけのロブスター)と呼ばれるが、ロブスターはイセエビよりもザリガニに近縁で、エビの分類上では別々に区分される。
硬い甲などの共通点もあるが、イセエビは大きな鋏脚を持たず、長い幼生期(後述)を経る点でロブスターとの差異がある。
<生態>
房総半島以南から台湾までの西太平洋沿岸と九州、朝鮮半島南部の沿岸域に分布する。かつてはインド洋・西太平洋に広く分布するとされたが、研究が進んだ結果他地域のものは別種であることが判明した。
外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息する。昼間は岩棚や岩穴の中にひそみ、夜になると獲物を探す。食性は肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を主に捕食するが、海藻を食べることもある。貝などは頑丈な臼状の大顎で殻を粉砕し中身を食べる。
一方、天敵は人間の他にも沿岸性のサメ、イシダイ、タコなどがいる。敵に遭うと尾を使ってすばやく後方へ飛び退く動作を行う。
繁殖期には他のイセエビの後をついて動くため列を作るという変わった生態がある。
(上記の説明は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
<イセエビの漁法>
イセエビは通常底さし網で捕獲します(イセエビは泳いでいるときに、網目に
しっぽから刺さるか、網にからまるかして捕獲されます)。
夷隅東部漁協のさし網漁は、昼間の1時に網を掛けに行き、翌日の夜中 の2時半に網を揚げに行き、港に戻ってイセエビなどの漁獲物をはずして 市場に出します。これで漁の終了ではなく、そのあとに、網が岩などにす れて切れてしまうので、午前中に網の修繕をします。
網の長さは船の乗組員の人数で決められており、例えば、3人乗りの船で78反 (=約1,950m、1反は約25m)までとなっており、網目も3.1寸 (9.3㎝)以上と決められています。このように、たくさん獲りすぎないように、 また、小さいエビを獲らないように工夫しています。
網を入れる場所は漁獲を左右する最大のポイント! 魚群探知機などで底の形状を見ながら、潮の流れなどを考えて、 根をはずさないように網を入れていきます。まさに長年の経験と最新の科学技術機器を駆使して イセエビを漁獲します。 (「イセエビの生態と漁法」より)
<イセエビの名前の由来>
現代では標準名は「イセエビ」とされていますが、江戸では鎌倉で獲れたものが届くのでカマクラエビ、京や大阪には伊勢から届くのでイセエビと呼ばれていたそうです。
その名前の由来としては諸説あり、例えば、伊勢湾でたくさん獲れたので、伊勢海老になったという説。
磯(いそ)にいるから(いそえび)がなまり、いせえびになったという説。
武士のかぶとの飾りが えびに似ていて 威勢がいいがなまったという説。
伊勢神宮に古くから海老が奉納されていたため、伊勢海老となったいう説。
ひげがピーンとのび威勢のいい海老というところから伊勢海老となったという説。
などなど、どの説ももっともらしいのですが、まことしやかにささやかれているのは、伊勢でたくさん採れたからだそうです。
<イセエビは日本の目出度さのシンボル>
『何が目出度いと言って、伊勢海老ほど目出度いものはありません。あの立派な長いヒゲ、腰を曲げて歩く姿、海の老人は長寿の象徴です。ましてや、武者の甲冑の見本となりそうな、見事な甲羅。もう目出度さの極みです。
と言うことで、正月のお飾りとご馳走、婚儀などあらゆる祝宴、神仏への供物、兜の前立て等々、イセエビの姿なしには日本の祝い事は始まりません。
ただ、際立った姿のために損?をしているのかも知れません。食べる前に味に過大な期待を抱かせてしまうのです。この姿なのだから食べたことがないほどの美味さなのだろうと。
「姿のイセエビ、味のクルマエビ」と言われるのは、味がクルマエビに劣ると言うより、自分の姿に勝てないということのような気がします。美味さは甲乙付けがたい程なのですから。』
(「旬魚余話」より)
☆ イセエビの捌き方
☆ イセエビの動画
☆ 巨大イセエビ
男性だってスキンケア バイオ基礎化粧品b.glen
詳細はこちら>>
Posted by きーさん at 08:01│Comments(0)
│甲殻類
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。