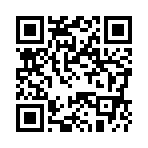2009年10月07日
魚名:オキエソ
さかな、サカナ、魚!
30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~


「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:40cm
学名:Trachinocephalus myops 英名:Ground spearing
地方名:モドロエソ、ドウナエソ
脊椎動物門-硬骨魚綱-ヒメ目-エソ科
分布:南日本~全世界の温帯・熱帯地域
<特徴>
成魚は全長40cmほど。吻が極端に短く、大きな目が頭部前面につく。口は大きく、顎には細かく鋭い歯が並ぶ。体型はエソ科に典型的な前後に細長い円筒形だが、マエソなどに比べると頭身が短くずんぐりしている。体の模様は黄色と水色の縦縞模様で、体の片側の黄色線は3-4本ある。不明瞭な暗色横斑が混じるものもいる。
腹鰭軟条の外側が短く内側が長いことと、尻鰭の基底が長いことで他のエソ科魚類と区別できる。エソ科の分類中では、1種のみでオキエソ属 Trachinocephalus として分類される。
<生態>
全世界の熱帯・温帯の海に広く分布する。日本でも南日本の暖流に面した地域で幅広く見られる。
水深100m以浅の砂底に生息するが、特に20m前後に多い。夜行性で海底付近を活発に泳ぎ、魚類や甲殻類を捕食する。餌生物は魚類が約75%、他のベントスが約15%を占めるというデータがある。昼は砂に浅く潜って休む。
産卵期は9-10月で、直径1.1-1.2mmの分離浮性卵を産む。稚魚は海岸近くの藻場にも見られるが、成長に従って深場に移る。
(上記2件の内容は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
このオキエソについては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。
『一般に食用とはしない。図鑑には生息域を南日本と漠然と書いている。関東、相模湾ではよく見かける魚だ。
本種は市場には、すり身材料として流通している。またその量は近縁のマエソと比べて少なく、鮮魚として売られているのは未だ見ていない。
釣り/この魚はキス釣りなどの外道(目的以外の魚)として馴染み深い。シロギスを釣っていると、そのシロギスをくわえて上がってくる。30センチを超える大物もいて、釣果の彩りにはなるが後で持て余す食えないヤツである。
ときに混ざってくるのを食べるべく挑戦してみた。刺身には小骨が多くてできない。塩焼きも水っぽい。仕方なくこんがりと唐揚げをつくる。これは香ばしくてなかなか捨てがたい味。ただし低温でじっくり揚げるしかない。』
また、「遊魚漫筆」では下記のような記述が見られます。
『オキエソは、世界に1属1種しかいない。この特徴的な顔つきのエソは、オキエソしかいないのだ。浅海にすむ小魚としては珍しく、全世界の温帯と、熱帯海域にすむ。汎世界分布なのである。
体側には淡青色と黄色の細い縦線が交互に走り、鰓蓋上端に黒色斑がある。エソ科にしては臀鰭基底が長い。顔つきと、これらの特徴で間違えることはない。
そうそう。エソ科魚類は脂鰭を持つ。背鰭の後方にある、1個の、鰭条(きじょう)を欠く肉質の鰭様突起物を脂鰭(あぶらびれ)という。
オキエソの脂鰭釣り人にはサケ目魚類にある脂鰭が有名である。
サケ科にはまって、みょうなエリート意識を持ってしまう釣り人がいる。彼らは、コイ科や、ほかの魚を狙う釣り人たちに「ぼくらは脂鰭族です、脂鰭のある魚しか狙いませんから…」などと見下したりする。
そういう釣り師には「へえ、エソが好きなんですか、変わってますねえ!」などと驚いてあげることにしている。
脂鰭を持つ魚類は、エソ科など、けっこう多い。変わったところでは、ピラニアなどのカラシン科も持っているし、ナマズの仲間も、立派な脂鰭を持つものが多い。
エソ科魚類は白身であるが、刺身などには小骨が多くてできない。肉質も水っぽい。そのために、ふつうの食べ方ができない魚である。
しかし、摘入(つみれ)などの練り製品にすると、これほど美味しい魚はない。愛媛県、宇和島の蒲鉾はエソ類を主原料として、美味しいことで知られている。
獰猛な魚食魚で、釣って面白い魚であると思うのだが、家庭で練り製品にするのは面倒であるし、それほど大量に釣れるものでもないので、もてあますことが多い。そのため、エソ類は釣れても、まったくの外道扱いである。
一般に浅海性のエソ類は貪欲であり、生きた魚でないと食べないといわれている。水族館での飼育は、かなり難しいらしい。
練り製品の材料の、どうしようもない餌盗りだと決めつけず、彼らの生態にも思いをはせようではないか。
憧れの魚を持つ釣り人は幸せである。
しかし、釣った魚のなかに、どうでもいい魚がいる釣り人は不幸である。
オキエソ。しっかり見つめて、ていねいに逃がそう。』
☆ オキエソの食べ方を研究してみた
☆ かまぼこ(蒲鉾)の作り方




30歳から始めるカラダの
アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より
大きさ:40cm
学名:Trachinocephalus myops 英名:Ground spearing
地方名:モドロエソ、ドウナエソ
脊椎動物門-硬骨魚綱-ヒメ目-エソ科
分布:南日本~全世界の温帯・熱帯地域
<特徴>
成魚は全長40cmほど。吻が極端に短く、大きな目が頭部前面につく。口は大きく、顎には細かく鋭い歯が並ぶ。体型はエソ科に典型的な前後に細長い円筒形だが、マエソなどに比べると頭身が短くずんぐりしている。体の模様は黄色と水色の縦縞模様で、体の片側の黄色線は3-4本ある。不明瞭な暗色横斑が混じるものもいる。
腹鰭軟条の外側が短く内側が長いことと、尻鰭の基底が長いことで他のエソ科魚類と区別できる。エソ科の分類中では、1種のみでオキエソ属 Trachinocephalus として分類される。
<生態>
全世界の熱帯・温帯の海に広く分布する。日本でも南日本の暖流に面した地域で幅広く見られる。
水深100m以浅の砂底に生息するが、特に20m前後に多い。夜行性で海底付近を活発に泳ぎ、魚類や甲殻類を捕食する。餌生物は魚類が約75%、他のベントスが約15%を占めるというデータがある。昼は砂に浅く潜って休む。
産卵期は9-10月で、直径1.1-1.2mmの分離浮性卵を産む。稚魚は海岸近くの藻場にも見られるが、成長に従って深場に移る。
(上記2件の内容は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
このオキエソについては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。
『一般に食用とはしない。図鑑には生息域を南日本と漠然と書いている。関東、相模湾ではよく見かける魚だ。
本種は市場には、すり身材料として流通している。またその量は近縁のマエソと比べて少なく、鮮魚として売られているのは未だ見ていない。
釣り/この魚はキス釣りなどの外道(目的以外の魚)として馴染み深い。シロギスを釣っていると、そのシロギスをくわえて上がってくる。30センチを超える大物もいて、釣果の彩りにはなるが後で持て余す食えないヤツである。
ときに混ざってくるのを食べるべく挑戦してみた。刺身には小骨が多くてできない。塩焼きも水っぽい。仕方なくこんがりと唐揚げをつくる。これは香ばしくてなかなか捨てがたい味。ただし低温でじっくり揚げるしかない。』
また、「遊魚漫筆」では下記のような記述が見られます。
『オキエソは、世界に1属1種しかいない。この特徴的な顔つきのエソは、オキエソしかいないのだ。浅海にすむ小魚としては珍しく、全世界の温帯と、熱帯海域にすむ。汎世界分布なのである。
体側には淡青色と黄色の細い縦線が交互に走り、鰓蓋上端に黒色斑がある。エソ科にしては臀鰭基底が長い。顔つきと、これらの特徴で間違えることはない。
そうそう。エソ科魚類は脂鰭を持つ。背鰭の後方にある、1個の、鰭条(きじょう)を欠く肉質の鰭様突起物を脂鰭(あぶらびれ)という。
オキエソの脂鰭釣り人にはサケ目魚類にある脂鰭が有名である。
サケ科にはまって、みょうなエリート意識を持ってしまう釣り人がいる。彼らは、コイ科や、ほかの魚を狙う釣り人たちに「ぼくらは脂鰭族です、脂鰭のある魚しか狙いませんから…」などと見下したりする。
そういう釣り師には「へえ、エソが好きなんですか、変わってますねえ!」などと驚いてあげることにしている。
脂鰭を持つ魚類は、エソ科など、けっこう多い。変わったところでは、ピラニアなどのカラシン科も持っているし、ナマズの仲間も、立派な脂鰭を持つものが多い。
エソ科魚類は白身であるが、刺身などには小骨が多くてできない。肉質も水っぽい。そのために、ふつうの食べ方ができない魚である。
しかし、摘入(つみれ)などの練り製品にすると、これほど美味しい魚はない。愛媛県、宇和島の蒲鉾はエソ類を主原料として、美味しいことで知られている。
獰猛な魚食魚で、釣って面白い魚であると思うのだが、家庭で練り製品にするのは面倒であるし、それほど大量に釣れるものでもないので、もてあますことが多い。そのため、エソ類は釣れても、まったくの外道扱いである。
一般に浅海性のエソ類は貪欲であり、生きた魚でないと食べないといわれている。水族館での飼育は、かなり難しいらしい。
練り製品の材料の、どうしようもない餌盗りだと決めつけず、彼らの生態にも思いをはせようではないか。
憧れの魚を持つ釣り人は幸せである。
しかし、釣った魚のなかに、どうでもいい魚がいる釣り人は不幸である。
オキエソ。しっかり見つめて、ていねいに逃がそう。』
☆ オキエソの食べ方を研究してみた
☆ かまぼこ(蒲鉾)の作り方
Posted by きーさん at 07:32│Comments(0)
│海の魚
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。